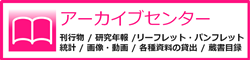目次
3 書類の書き方等
1 認定薬局制度について
| Q1 健康サポート薬局と認定薬局の違いは何ですか? |
かかりつけ薬剤師・薬局の機能は共通ですが、それぞれ次のような特徴があります。 【健康サポート薬局】 【地域連携薬局】 【専門医療機関連携薬局】 |
|
Q2 認定を受けることにより何が変わりますか? |
認定を受けた薬局は「地域連携薬局」または「専門医療機関連携薬局」と称することができます。 |
|
Q3 認定を取得するメリットは何ですか? |
認定を取得し、認定薬局の名称や機能を薬局内外の掲示や薬局機能情報提供制度で公表することにより、地域住民や医療・介護関係職種からの信頼やかかりつけ薬局の選択につながる可能性が期待されます。 |
2 申請方法等について
| Q1 申請手続きをするには、何をすればよいですか? |
申請に当たっては、法令等に基づき、基準に適合した構造設備や体制を整えることが必要です。 |
| Q2 申請場所はどこですか? |
東京都健康安全研究センター本館1階(住所:新宿区百人町3-24-1)です。 |
|
Q3 郵送での申請は可能ですか? |
手数料が必要となる申請については郵送による書類の受付はできません。直接窓口へお持ちいただくか、オンライン申請をご利用ください(島しょの方は個別にご相談ください。)。 |
|
Q4 窓口で申請手続きをする場合、どれくらい時間がかかりますか? |
申請件数や窓口の混雑状況により待ち時間は異なります。 |
|
Q5 窓口で申請手続きをする場合、予約は必要ですか? |
原則不要です。 |
|
Q6 申請手数料はいくらですか? |
申請の種類により手数料が異なります。「手数料一覧」をご確認ください。 |
|
Q7 申請した書類の控えを窓口で受け取れますか? |
都では申請書の控えは作成しません。申請書の控え(添付資料含む)が必要な場合には、申請者様でご準備ください。 |
|
Q8 構造設備が未完成でも申請はできますか? |
申請書には薬局の平面図及び実際の設備が確認できる写真等を添付する必要があるため、原則できません。 |
|
Q9 認定書は、申請書を提出したらその場で交付されるのですか? |
その場での交付はされません。 |
| Q10 どのような方法で認定証が交付されるのですか? |
窓口交付又は郵送交付です。 |
|
Q11 返信用封筒はどのようなものを準備したらいいですか? |
宛先の郵便番号、住所、氏名を記入した角2型の封筒(A4サイズが折らずに入る大きさ)に返信用切手(郵便料金+簡易書留料金)を貼付した封筒をご準備ください。 なお、レターパックはお預かりできませんのでご注意ください。 |
| Q12 申請した内容に誤りや不備があった場合は、どうしたらよいですか? | 申請内容に誤り等があった場合、受付窓口で修正依頼をすることがあります。また、審査中に疑義等が生じた場合には書類の差換えをお願いすることがあります。 この場合、担当者からの修正依頼に従って必要な手続きを行ってください。 修正方法等については、その内容や状況により異なります。 |
|
Q13 申請手続きについて聞きたいのですが、どこに連絡をすればよいですか? |
【都内の薬局の場合】 【薬局所在地が東京都以外の場合】 |
3 書類の書き方等
|
Q1 書類作成上の注意点はありますか? |
文書の改ざん防止のため、消えるボールペンや鉛筆等は使用しないでください。 |
|
Q2 申請書に押印は必要ですか? |
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)」が公布、施行されたことに伴い、申請書様式への押印は不要です。 |
|
Q3 添付書類に記載されている個人情報をマスキングする必要はありますか? |
必要です。マスキングがされていない書類を受け取ることはできません。 【個人情報の例】 |
|
Q4 添付する資料の写しは撮影画像でもよいですか? |
原則、複写機を使用してコピーした書類等をご提出ください。 |
|
Q5 認定適合基準表はどのように記載するのですか? |
認定基準適合表の記載方法は「申請様式ダウンロード(地域連携薬局)」又は「申請様式ダウンロード(専門医療機関連携薬局)」をご確認ください。
|
|
Q6 「高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造設備」のチェックボックス欄は全てにあてはまらないといけないのですか? (参考:地域連携薬局認定基準適合表No.2、専門医療機関連携薬局(がん)認定基準適合表No.2) |
認定基準適合表のチェックボックス欄に記載された設備は通知で示された具体例であり、できるだけ多くの項目に該当することが望ましいものの、必ずしも全ての項目に該当しないと認定が下りないわけではありません。 |
|
Q7 構造設備に係る添付書類は該当する構造設備の写真のみでよいですか? |
写真の他、薬局の平面図も必要です。 |
|
Q8 「地域における医療機関に勤務する薬剤師等に対して報告及び連絡した実績」のうち、「在宅訪問時」はどのように計上すればよいですか? (参考:地域連携薬局認定基準適合表No.5) |
患者の居宅等を訪問して情報提供や指導を行い、その報告書を医療機関へ提供して情報共有を行った回数を実績として計上してください。 |
|
Q9 「居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の実績」はどのように計上すればよいですか? (参考:地域連携薬局認定基準適合表No.16) |
居宅等を訪問して指導等を行った回数を実績として計上してください。 |
|
Q10 「常勤として勤務している薬剤師数」は、いつの時点での薬剤師数をいうのですか? (参考:地域連携薬局認定基準適合表No.13、専門医療機関連携薬局(がん)認定基準適合表No.11) |
認定申請時又は認定更新申請時における人数です。 |
|
Q11 「常勤として勤務している薬剤師」にはどのような人が該当しますか? (参考:地域連携薬局認定基準適合表No.13、専門医療機関連携薬局(がん)認定基準適合表No.11) |
認定薬局制度における「常勤」は週当たり32時間以上※の勤務をいいます。 ※育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づく所定労働時間の短縮等、例外として週32時間未満の勤務でも「常勤」として取り扱う場合があります。詳細は事務連絡の問13をご確認ください。 |
|
Q12 「継続して1年以上勤務している常勤薬剤師」にはどのような人が該当しますか? (参考:地域連携薬局認定基準適合表No.13、専門医療機関連携薬局(がん)認定基準適合表No.11) |
申請の前月までに継続して1年以上常勤として当該薬局に勤務している方が「継続して1年以上勤務している常勤薬剤師」に該当します。 |
|
Q13 「地域包括ケアシステムに関する研修」とは何ですか? (参考:地域連携薬局認定基準適合表No.13) |
「健康サポート薬局に係る研修実施要綱」に基づき実施される健康サポート薬局に係る研修が該当します。研修実施機関は、下記の厚生労働省指定確認機関のホームページからご確認ください。 【指定確認機関】公益社団法人日本薬学会 |
|
Q14 「地域包括ケアシステムに関する内容の研修」とは何ですか? (参考:地域連携薬局認定基準適合表No.14) |
地域包括ケアシステムに係る内容が学習できる研修です。 |
|
Q15 「専門的な医療の提供等を行う医療機関」及び「がん治療に係る医療機関」とは何ですか? (参考:専門医療機関連携薬局(がん)認定基準適合表No.3) |
厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等及び都道府県が専門的ながん医療を提供するものとして認めた医療機関のことです。 |
|
Q16 がんに係る「専門性を有する薬剤師」を認定する団体はどこですか?また、当該団体が認定する専門性の名称は何ですか? (参考:専門医療機関連携薬局(がん)認定基準適合表No.11) |
厚生労働大臣に届出がなされているのは以下の2団体です。 ・一般社団法人日本医療薬学会 |
4 薬局開設者変更や移転に伴う申請について
| Q1 薬局開設者の変更や薬局の移転に伴い薬局開設許可を新しく受けました。地域連携薬局等の認定は再度申請しなおす必要がありますか? |
地域連携薬局等は薬局開設許可に紐づく認定となっているため、移転等に伴い新たに薬局開設許可を受けた場合には、地域連携薬局等の認定についても改めて申請し、再度認定を受ける必要があります。 |
|
Q2 薬局開設者の変更に伴い新たに地域連携薬局等の認定を受けたいのですが、元々の薬局における実績を引き継ぐことはできますか? |
変更事項が薬局開設者の変更のみであり、薬局の所在地、薬局に勤務する薬剤師等の勤務状況が同じである等、変更前後で認定薬局の機能に変更がなく、薬局の業務の体制が引き継がれている場合には元々の薬局における実績を引き継ぐことが可能です。 |
|
Q3 薬局の移転に伴い新たに地域連携薬局等の認定を受けたいのですが、元々の薬局における実績を引き継ぐことはできますか? |
以下の3つの要件を満たす場合、元々の薬局における実績を引き継ぐことが可能です。 ・当該薬局に勤務する薬剤師等の勤務状況が同じである |
|
Q4 薬局開設者の変更や薬局の移転に伴い新たに地域連携薬局等の認定申請をする場合、通常の申請とは別に用意する必要のある書類はありますか? |
上記Q2、Q3に該当し、元々の薬局における実績を引き継いで認定申請を行う場合、薬局の業務の体制が引き継がれていること等を申告いただく書類が必要となります。 ・薬局開設者変更:地域連携薬局/専門医療機関連携薬局 |
問い合わせ先
東京都健康安全研究センター 広域監視部薬事監視指導課 連携薬局担当
住所:〒169-0073 東京都新宿区百人町3-24-1 本館1階
電話:03-3363-3938
e-mail:S1153808※section.metro.tokyo.jp
※を@に置き換えてメールをお送りください。