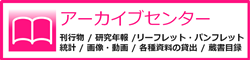モミジガサとトリカブト類
モミジガサとトリカブト類(有毒)
 |
 |
|||
| モミジガサの芽生え | トリカブト類の芽生え | |||
| 芽生えはトリカブト類にとても似ています。東北ではシドケと呼び、葉が展開する前の若い茎葉をゆでて、山菜として利用します。 | 成長するにつれ、花茎が立ち上がります。 | |||



モミジガサ 花期 トリカブト類 花期
モミジガサは山地の林に自生するキク科の多年草です。草丈90㎝位で、夏に茎上部で分岐し、円錐状に白い小さい花(頭花)を付けます。
トリカブト類は山地の林等に自生するキンポウゲ科の多年草です。草丈は1m内外で、花を付ける頃には茎が下垂します。9月〜10月頃、茎頂の葉腋に紫色の花を多数付けます。
トリカブトの名前は、花の形が舞楽の時に使う伶人の冠に似ているところから名付けられました。
植物全体、特にその芽、葉にもアコニチンなどのアルカロイドを含有しており、誤食すると、嘔吐、下痢、手足や指の麻痺の中毒症状を起こし、重症の場合には死亡することもあります。
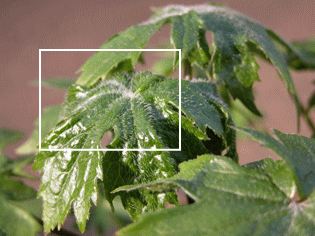
モミジガサの若葉
モミジガサの芽生えの頃の葉の表面には細かい毛が生えています。
モミジガサとトリカブト類の見分け方
- モミジガサ(含むテバコモミジガサ)とトリカブト類の芽生えは非常によく似ています。初心者は間違えやすいので、採取は止めましょう
- モミジガサの芽生えには葉の表面に細かい毛が生えていますが、トリカブト類の葉は、ほぼ無毛です。
- モミジガサとテバコモミジガサの葉は掌状で、基部まで切れ込みません。トリカブト類の葉は、5角形状で、3または5に深く裂けます。ただし、トリカブトの仲間には、葉が深く裂けないものもあります。
モミジガサとテバコモミジガサ
テバコモミジガサは最初にみつかった高知県の手筥山にちなんで名付けられました。モミジガサによく似ていますが、全体が細やかで、つる枝があることで見分けられます。一般にはモミジガサと区別されずに山菜として利用されていると思われます。
テバコモミジガサの葉は切れ込みが深く、トリカブト類の葉に極似し、また、トリカブト類と同じ場所(沢沿い)に生えていることもあるので、特に注意が必要です。
©東京都薬用植物園