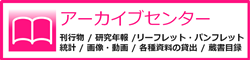皆さんは、薬局をどのように利用していますか?
薬局はたくさんあり、自由に選ぶことができますが、いつも利用する薬局「かかりつけ薬局」を持つと、いろいろなメリットがあります。
ここでは、薬局の機能やかかりつけ薬局の役割を紹介します。
薬局まめ知識
薬局は、かぜ薬や胃腸薬などの医薬品や、化粧品、健康食品を売っているお店、というだけではありません。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)という法律の規定に基づいて担ってる、さまざまな役割を紹介します。
医薬分業って何だろう?
「医薬分業」とは、医師(歯科医師)と薬剤師の二人の専門家により、医薬品の使用を二重にチェックし、患者さん一人一人に処方された薬の効果や安全性を一層高めようとする制度です。医薬分業によってどのようなメリットがあるのか、紹介します。
かかりつけ薬局のメリット
かかりつけ薬局は、皆さんの適正・適切な服薬をお手伝いします。どのような仕事をしているのか、紹介します。
薬局についての疑問点は?
薬局のことでわからないこと、疑問に思うことがある場合には、薬局のある場所を所管する保健所にご連絡ください。
- 都内保健所連絡先 23区 多摩地区・島しょ地区
かかりつけ薬局指針(東京都)
かかりつけ薬局の育成を目的として、国では「薬局業務運営ガイドライン」を示しており、東京都でもこれに基づいて医薬分業の普及・定着を支援してきました。また、ガイドライン制定後の状況の変化等を加味し、東京都独自に「かかりつけ薬局指針」を示しています。
この指針は、掲げている取組内容すべてを一律に薬局に対して求めているものではありません。それぞれの薬局が地域性や特性を活かし、信頼される薬局を目指して必要な項目を選んで充実を図っていくものです。
皆さんの薬局選びの参考にしてください。
薬局まめ知識
薬局の機能とは
1 薬剤師が、販売又は授与の目的で調剤を行う場所を薬局といいます。
![]() 調剤ってどういうこと?
調剤ってどういうこと?
調剤とは、「医師、歯科医師の発行する処方箋に従って、1種類以上の薬品を配合し若しくは1種類の医薬品を使用し特定の分量に従い特定の用法に適合するように特定の人の病気疾病に対する薬剤を調整すること」です。
2 薬局は、「調剤」のほかに「医薬品」を取扱う(販売する)ことができます。
3 薬局には、必ず薬剤師がおり、薬の使い方や健康の維持・増進などについて相談することができます。
4 医薬品に関するいろいろな情報(副作用や薬の飲み合わせで注意することなど)の提供が受けられます。
5 その他
薬剤師の専門性を活かした皆さんへの利便性、サービスのため、染毛剤、浴用剤などの医薬部外品や化粧品などを扱っている薬局もあります。
また、最近では、在宅介護を支援するサービスを行っている薬局も増えています。
医薬分業って何だろう?
「医薬分業のメリット」
医師や歯科医師が発行した処方箋を、街の保険薬局に持っていくと、薬剤師は処方箋に基づいて、薬の量や飲み合わせ等を確認のうえ、調剤を行います。
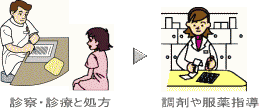
医薬分業は、次のようなメリットを感じてもらえるように進められています。
1 薬の専門家である薬剤師から、薬の適正使用のための充分な服薬指導を受けることができます。
2 薬の相互作用や重複投与による副作用を未然に防止し、安全な使用が確保できます。
3 調剤してもらう薬局は、患者さんの自宅や職場の近くなどで、自由に選ぶことができます。
4 薬の専門家である薬剤師が医薬品を管理することで、その安全性及び有効性の一層の確保が期待できます。
5 診察が済めば処方箋をお渡ししますので、自分の都合に合わせて薬局に処方箋をもっていき、薬を受け取ることができます。
6 医療機関においても、医師(歯科医師)が診断、治療に専念することができ、医療がより充実することが期待できます。
また、医師が自由に薬を処方できるため、処方する薬の幅が広がります。
![]() 処方箋とはどういうもの?
処方箋とはどういうもの?
処方箋とは、薬の種類やその量及び使い方を記入したものです。処方箋には有効期限があり、交付の日を含めて4日以内に調剤をしてもらわなければ失効してしまいます。
かかりつけ薬局のメリット
かかりつけ薬局のメリット=医薬分業のメリット
どこの薬局を利用するか自由に選ぶことができますが、いつも利用する薬局「かかりつけ薬局」を持つことで、薬をより安全に利用できます。かかりつけ薬局をつくることにより、これまで進めてきた医薬分業のメリットを皆さんが得ることができます。
1 あなたの「薬歴(薬の服用記録)」を作ります。
2 薬の重複投与や相互作用による副作用などの健康被害の未然防止が図られます。
![]() 重複投与とは?
重複投与とは?
複数の医療機関にかかっている場合に、作用の同じ薬をそれぞれの医療機関から処方されるようなことを指します。かかりつけ薬局では、薬歴の管理により、同じ薬を何種類も飲んでいないかチェックします。
![]() 相互作用とは?
相互作用とは?
ここでは、医薬品と医薬品の飲み合わせによって、お互いの効き目が強まったり弱まったりしてしまうことを言います。医薬品の中には、特定の医薬品と一緒に使わないように、特に注意をしなければいけないものがあります。
3 病院・診療所の医師(歯科医師)の発行する処方内容を知ることができます。
薬についてわかりやすく説明します。薬の名前や効き目などを書いたメモをお渡しすることもあります。
4 薬の飲み方、使い方、副作用についてなど、服薬指導をいつでも受けられます。
5 健康に関する情報の提供が受けられます。
処方箋なしで買うことができる薬(一般薬)との飲み合わせや健康食品についてなど、街の科学者として皆さんの疑問にお答えします。
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 食品医薬品情報担当 です。