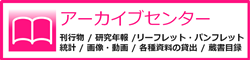健康食品を取り扱いたいけれど、いろいろな法律が関わっていて、どんな点をどのように注意すればいいのか分からない・・・、都の相談窓口にこのような声がよく届けられます。しかし、そうはいっても、仮に法令に違反してしまったら、知らなかったでは済みません。そこで、このページでは、健康食品を取り扱う際に気をつけなければいけないポイントや相談窓口をご紹介します。
関係する法令の概要を知りたい
健康食品を取扱う際は、複数の法令に注意を払う必要があります。以下に健康食品の製造等に関係する主な法律名を挙げました。製品によっては、これ以外の法律又は条例(例:都内事業者の方には東京都食品安全条例が適用されます。)の適用を受けることもありますので、取扱い事業を行う前に、各自でお調べください。
- 食品衛生法
- 食品表示法
- 健康増進法(栄養成分表示、誇大広告の禁止)
- 医薬品医療機器等法
- 景品表示法(東京くらしWEBへリンク)
- 特定商取引法(東京くらしWEBへリンク)
健康食品の取扱いに関するご質問等は、各法令の所管部署にお問い合わせください。
製造・輸入・販売についての規制(許可、届出等)を知りたい
- 食品衛生法により、 食品を製造、販売する際には、取り扱う食品の種類によって許可等が必要な場合があります。許可等の種類や手続きについては「食品衛生の窓」のページをご覧ください。
- 健康食品を輸入する際には、そのつど、厚生労働大臣(検疫所)に届け出なければなりません。詳細は、厚生労働省の各所管検疫所にお問い合わせください。。
- 訪問販売や通信販売など、特定の販売形態については、特定商取引法において消費者保護等の観点から必要な表示事項や禁止行為等が定められています。詳細は消費者庁のページをご覧ください。
インターネット通販(オークションを含む)を考えている
インターネットで通信販売を行う場合や、インターネットオークションに出品する場合には、守るべきルールがあります。詳細は消費者庁のページをご覧ください。
原材料、形状等についての規制(使用可能な成分等)を知りたい
食品の規格基準等について
食品衛生法により、食品には一般的な成分規格が定められています。また、清涼飲料水等のように、食品の種類によっては更に詳細な成分規格や製造基準が定められています。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
食品添加物の使用について
食品添加物は、原則として指定されたもの以外は使用することができません。また、指定されたものでも、使用に当たっては量や対象食品等が限定されている場合があります。食品添加物に関する詳細は、「食品衛生の窓」をご覧ください。
医薬品に該当する成分について
医薬品成分(詳細は薬務課のホームページをご覧ください。)を含有した物は、たとえ「健康食品」として製造、輸入、販売したとしても、医薬品とみなされます。
医薬品的な形状について
アンプル剤の形をしている物等、消費者に医薬品と誤認されやすい形状は食品には認められていません。医薬品的な形状に関する詳細は、薬務課のホームページをご覧ください。
錠剤、カプセル状等の食品の取扱い
錠剤、カプセル状等の形状の食品については、原材料等の成分が濃縮されるという特性があります。このため、安全性確保の観点から適正な製造行程管理及び原材料の安全性確保についての一定のガイドラインがあります。詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
表示・広告についての規制や注意点
健康食品の表示には、通常の食品と同様に、食品表示法で定められた表示事項について、基準に合った表示を行う必要があります。一方、定められた表示事項以外の任意で行われる表示や広告については、医薬品医療機器等法や景品表示法等で表現できないことが定められています。食品表示については、「衛生事項」(元は食品衛生法に定めがあった事項)、「品質事項」(元はJAS法に定めがあった事項)及び「保健事項」(栄養成分表示など、元は健康増進法に定めがあった事項)に大きく分けられて規定されています。東京都では、事業者の方向けに「食品の表示制度」というページを開設していますので、詳細はそちらをご覧ください。
保健機能食品制度について知りたい
栄養機能食品、特定保健食品(トクホ)や特別用途食品に関する制度については、消費者庁が「健康や栄養に関する表示の制度について」というページで詳細な情報を提供しています。
機能性表示食品について
平成27年度から始まったもので、消費者庁が所管する制度です。制度の趣旨、届出等の手続きなど、詳細は消費者庁のホームページをご覧ください。
問合せ先:東京都健康安全研究センター企画調整部健康危機管理情報課食品医薬品情報担当
電話:03-3363-3472
FAX:03-5386-7427
メールアドレス:S1153803<at>section.metro.tokyo.jp
※<at>を@に置き換えてメールをお送りください。