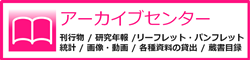食品表示法による表示(食品表示法)
Q1 商品名を名称として記載したり、名称に括弧を付して商品名を併記することはできますか。
食品表示基準において、名称は、その内容を表す一般的な名称で記載するよう規定していますので、商品名がその内容を表す一般的な名称であれば、名称に使用することは可能です。また、食品表示法以外の法令により表示規制のある品目については、当該法令により制限を受けることがあります。名称に括弧を付して商品名を併記することについては、併記することにより名称を誤認させるものでなければ、差し支えありません。
Q2 食品表示基準における食品関連事業者の項目名について、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称の表示との関係を教えてください。
加工食品について、その表示内容に責任を持つ者(食品関連事業者)の氏名又は名称及び住所を表示することが規定されています。一方、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称については、食品を摂取する際の安全性の確保の観点から、表示することが規定されています。これらの規定は目的が異なっていることから、表示に責任を持つ者の氏名又は名称及び住所と、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称を、それぞれ適切な項目名で表示することが必要となります。表示内容に責任を持つ者の氏名又は名称及び住所と、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称とが同一である場合には、その事業者名を表示することで両規定を満たしているものとみなされます。一方、両規定により表示する者が異なる場合は、表示内容に責任を持つ者の氏名又は名称及び住所を食品表示基準別記様式1の枠内に表示することが必要です。なお、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称についても食品表示基準別記様式1の枠内に表示することは可能ですが、この場合、どちらの者が表示に責任を持つ者であるかを合意しておく必要があります。また、表示責任者は1者となりますが、温度帯を変更するなど部分的に表示の変更を行う場合は、その表示事項について、変更した者が責任を負うことになります。なお、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称は、表示内容に責任を持つ者の名称等に近接して表示しなければならないことが規定されています。
Q3 製造者と表示責任者(販売者)が異なる場合の表示方法について具体的に教えてください。
食品表示基準第3条第1項の表に規定しているとおり、一般用加工食品を販売する場合「販売 者の氏名又は名称及び住所」に加えて、これまでどおり、公衆衛生上の危害発生・拡大防止の観 点から「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」を表示する必要があります。その際、「製 造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」は「販売者の氏名又は名称及び住所」に近接して表示 する必要があります。具体的には以下の表示方法が考えられます。
Q4 外国(A 国)で製造された加工食品を別の外国(B 国)を経由して輸入した場合、食品表示基準では原産国名はどちらを表示すべきですか。
この場合、B 国は経由するだけで、実質的な変更をもたらす行為を行っていないことから、原産国としては最終的な製造国であるA国を表示することとなります。なお、関税法(昭和29 年法律第61 号)においても最終加工地を原産国と規定しています。
Q5 栄養強調表示をする成分以外の栄養成分について、合理的な推定により得られた値を表示することができますか。
一般加工食品について栄養成分の機能の表示や栄養強調表示をする場合は、強調される栄養成分だけでなく、表示するすべての栄養成分及び熱量についても、合理的な推定により得られた値で表示することは認められません。
Q6 一般用加工食品について、栄養成分の機能の表示や栄養強調表示をしない場合、一つの食品の栄養成分表示の中に、一部の項目のみ合理的な方法による推定値で表示することは可能ですか。その場合、保管しておく合理的根拠は「推定値」の表示を行った成分のみでよいですか。
「推定値」である成分が分かるように記載すれば問題ありません。例えば「○○は推定値」、「○○以外の栄養成分については、推定値」等の文言を、栄養成分表示に近接した場所に記載してください。「推定値」の表示を行った成分については、必要に応じて説明ができるようにその合理的根拠を保管しておく必要があります。
Q7 容器包装に、一般的に知られていることを謳った場合(例:「みかんにはビタミンC がたくさん含まれます」「牛乳にはカルシウムが豊富」)、栄養強調表示の規定に従った表示が必要となりますか。
消費者庁のホームページ上に記載されている食品表示基準別表第12、別表第13 の第1欄に掲げる栄養成分について栄養強調表示をする場合、食品表示基準に従って表示する必要があります。なお、栄養強調表示をせずに単に栄養成分の名称を記載した場合は、基本5項目(熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量)及び表示した栄養成分の量の表示が必須です。
Q8 特色のある原材料を使用した場合、必ず使用割合を表示しなければならないのですか。
1 割合表示が必要となるのは、特色のある原材料を使用したことを強調して表示する場合です。特色のある原材料を使用していても、そのことを表示しないのであれば割合表示を行う必要はありません。
2 具体的には、特色のある原材料(○○)を使用して、
① 製品表面などに「○○使用」、「○○入り」のように、特色のある原材料を強調して表示する場合
② 製品の名称が特色のある原材料を使用した旨を示すものである場合
③ 「○○を使用し、…」のように説明書きなどで特色ある原材料を使用した旨を表示する場合
④ 一括表示部分の原材料名として「うるち米(○○)、…」のように表示する場合 には、○○の使用割合を明示することが必要です。
3 また、同種の原材料中における使用割合が100 %である場合には、割合の表示を省略することが可能です。
Q9 A県産のりんご果汁とB 県産の濃縮りんご果汁を使用した製品に、A 県産のりんご果汁を使用した旨を表示する場合には割合の表示が必要ですが、使用した状態で重量の比較をすればいいのですか。
1 状態(濃縮、乾燥など)の異なる同種の原材料を混合して使用する場合には、使用した状態で重量比較を行うのではなく、同等の状態に換算した重量の比較を行ってください。
2 問の例の場合、使用した状態で重量の比較を行うとA 県産の割合が多くなり、消費者に誤認を与えることとなるので、B 県産の濃縮りんご果汁を還元した状態の重量に換算するなど適切に比較を行った上で表示することが必要です。
Q10 使用割合が変動する原材料を特色のある原材料として表示したい場合、どのように割合表示を行えばよいですか。
1 原材料の使用割合が変動する場合、想定される最小値を記載し、「○%以上」又は「○割以上」のように幅をもたせた表示を行うことが可能です。
2 具体的には、例えば、季節により使用割合が45 %〜52 %の範囲で変動する特色のある原材料を強調して表示する場合には、「45 %以上」又は「4割以上」の表示が可能です。
3 なお、「○%〜△%」のように表示することは、含有量が多いとの誤認を与える可能性があることから認められません。
食品表示法による表示(食品表示法)のQ&Aに関する問合せ先:所管の担当部署
栄養成分表示(保健機能食品を除く)(食品表示法)
Q1 ナトリウム塩を添加していない食品の栄養成分表示(食品表示基準別記様式3)において、ナトリウムを任意で表示する場合、食塩相当量を枠外に記載することは可能ですか。
できません。食塩相当量も一括表示内でナトリウムのあとに括弧書きで表示してください。
栄養成分表示(保健機能食品を除く)(食品表示法)のQ&Aに関する問合せ先:所管の担当部署
表示・広告禁止事項
- 全般的な表示・広告禁止事項
Q1 インターネット上で行う健康食品の広告も、テレビ、新聞、雑誌等と同様に規制対象となりますか。(医薬品医療機器等法・健康増進法・景品表示法・特定商取引法)
医薬品医療機器等法
顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であり、商品名が明らかにされ、一般人が認知できる状態である場合には、広告に該当し、他の媒体と同様に規制の対象となります。インターネット広告については、リンク先の内容も同一広告の一部とみなします。
健康増進法
健康増進法上の表示とは顧客を誘引するための手段として行う広告その他の表示であり、インターネット上での広告も対象となります。
景品表示法
インターネット上で行う広告も、不当景品類及び不当表示防止法第2条第4項に規定する表示にあたるため、規制の対象となります。
特定商取引法
販売方法「通信販売」は特定商取引法第2条第2項に該当するため、規制の対象となります。
全般的な表示・広告禁止事項のQ&Aに関する問合せ先一覧:各法令の所管部署(都内事業者向け)
- 医薬品医療機器等法に関する表示・広告禁止事項
Q1 製品の原材料の効能等が書かれた書籍を製品と一緒に配布することは問題がありますか? (医薬品医療機器等法)
医薬品的な効能効果を説明した書籍を、製品販売時に手渡したり、製品送付時に同封することは、医薬品的な効能効果を標ぼうしたことになるため医薬品医療機器等法に抵触します。
Q2 タコには、もともとタウリン(医薬品成分)が含まれているので、製品表示やパンフレット等に「商品名:○○○の原料であるタコには、滋養強壮によいと言われているタウリンが含まれています。」といった内容を標ぼうしてもよいですか。 (医薬品医療機器等法)
医薬品成分であるタウリンは、強調的標ぼうに当たらない場合などの例外を除き、含有する旨の標ぼうはできません。なお、強調的標ぼうについては平成28年9月16日付厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課事務連絡「『専ら医薬品成分』の強調的標ぼうに係る判断事例について」を参考にしてください。
Q3 次のような内容を標ぼうしてもよいでしょうか。「ケールには、ビタミン(ビタミンC 等)やミネラル(鉄、亜鉛等)をはじめ今、話題のメラトニンなどの栄養素が含まれています。」(医薬品医療機器等法)
医薬品医療機器等法上、ビタミン・ミネラルは非医薬品成分であるため、食品中に含まれる旨を標ぼうをすることは差し支えありません。しかし、メラトニンは医薬品成分(ホルモン)ですので、強調的標ぼうに当たらない場合などの例外を除き、メラトニンを含有する旨の標ぼうはできません。
また、ビタミンなど食品表示法(食品表示基準)で定められた栄養成分に関する表示を行う場合は、食品表示法に従った栄養成分表示が必要になります。栄養成分表示の方法については、東京都のホームページ上等を参考にしてください。
Q4 低カロリー食品を開発し、販売するに際して、この食品は「糖尿病の方に最適」と表示したいのですが、できますか。(医薬品医療機器等法)
低カロリーというだけで糖尿病の人に客観的に最適といえるかどうかもさることながら、糖尿病治療効果を標ぼうすることは医薬品医療機器等法に抵触するおそれがあります。
また、「糖尿病の方に最適」という表現について医師又は歯科医師の診断、治療等によることなく疾病を治癒できるかのような表示は、健康増進法に抵触するおそれがあります。
Q5 輸入予定の食品の原材料が医薬品成分に該当しないか検疫所等から確認を求められているのですが、製品規格書等を薬務課で確認してもらうことはできますか。(医薬品医療機器等法)
事業者の方の責任の下においてリストと照合していただき、医薬品成分が含まれていないことを担保してください。
医薬品医療機器等法に関する表示・広告禁止事項のQ&Aに関する問合せ先
保健医療局健康安全部 薬務課監視指導担当
電話:03-5320-4512
| 「第4章 Q&A」のページの管理は、 東京都健康安全研究センター企画調整部健康危機管理情報課食品医薬品情報担当です。 電話:03-3363-3472(直通) メールアドレス:S1153803※section.metro.tokyo.jp ※を@に置き換えてメールをお送りください。 |