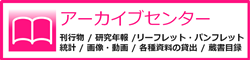第5章 Q&A
1 保健機能食品制度とは (食品表示法)
Q1 保健機能食品の表示が望ましくない食品はありますか。
例えば、ビール等のアルコール飲料や、ナトリウム、糖分等を過剰に摂取させることになる食品は、保健機能食品の表示をすることによって、当該食品が健康の保持増進に資するという一面を強調することになりますが、摂取による健康への悪影響も否定できないことから、保健機能食品の表示をすることは望ましくないと考えます。
Q2 保健機能食品以外の食品については、保健機能食品と紛らわしい名称を表示してはならないこととされていますが、紛らわしい名称とは、具体的にはどのようなものですか。
例えば、「特定健康食品」、「特定機能食品」、「保健○○食品」、「機能○○食品」等の名称で、特に「機能」、「保健」の文字が含まれているものを指します。
Q3 「保健機能食品の必要表示事項である特定の対象者に対し注意を必要とするものにあっては、当該注意事項」とは、どのような表示ですか。
疾病により栄養代謝に変化が生じ、健康な者と同等の栄養成分の機能が得られないようなもの、妊産婦や乳幼児等、特定のライフステージにある者について摂取量に注意が必要なものについて、その旨を表示してください。
例えば、グレープフルーツ(ジュース)は、カルシウム拮抗薬の効果を増強する可能性がある等の表示が考えられます。
2 栄養機能食品 (食品表示法)
Q1 栄養機能食品において、規格基準が定められている栄養成分を複数表示する場合、その順序は決められていますか。
特に決められていません。
Q2 栄養機能食品において、1日当たりの摂取目安量を「○○粒~○○粒お召し上がりください。」という旨の幅の両端をもって表示することは可能ですか。また、「~以上お召し上がりください。」、「~以内をお召し上がりください。」という旨の幅の一端のみをもって表示することは可能ですか。
幅の両端をもって表示することは可能です。
ただし、この場合においては、幅の両端それぞれの1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養機能表示成分量が、栄養機能食品の規格基準に適合する必要があります。
一方、幅の一端のみをもって表示することは、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養機能表示成分量が、栄養機能食品の規格基準の上限値と下限値をはずれる可能性があるので、当該基準を満たすことにはなりません。
このページのQ&Aに関する問合せ先:各法令の所管部署(都内事業者向け)
| 「第5章 Q&A」のページの管理は、 東京都健康安全研究センター企画調整部健康危機管理情報課食品医薬品情報担当です。 電話:03-3363-3472(直通) メールアドレス:S1153803※section.metro.tokyo.jp ※を@に置き換えてメールをお送りください。 |