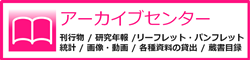医薬部外品は製造販売業許可のみでは製品の製造販売を行うことはできず、品目ごとの医薬部外品製造販売承認を取得する必要があります(「承認不要医薬部外品基準(平成9年3月24日厚生省告示第54号)」にあてはまる清浄綿を除く)。
製造販売承認審査では、申請者が製造販売を行おうとする製品の成分や効果等について、医薬部外品として妥当かどうか判断されます。例えば、目的としている効果等が医薬部外品の範囲から外れてしまっている場合は承認されません。
よって、医薬部外品製造販売承認を申請する際は、申請品目が医薬部外品の範囲(医薬品医療機器等法第2条第2項)に該当していることや下記の条件を満たすことを申請者自ら確認する必要があります。
医薬部外品についての医薬品医療機器等法の定義
(医薬品医療機器等法第2条第2項)
医薬品医療機器等法で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であって人体に対する作用が緩和なものをいう。
一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であって機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの(昭和36年厚生省告示第14号)
| 一 | 胃の不快感を改善することが目的とされている物 | ○ |
|---|---|---|
| 二 | いびき防止薬 | ○ |
| 三 | 衛生上の用に供されることが目的とされている綿類(紙綿類を含む。) | |
| 四 | カルシウムを主たる有効成分とする保健薬(第十九号に掲げるものを除く。) | ○ |
| 五 | 含嗽(そう)薬 | ○ |
| 六 | 健胃薬(第一号及び第二十七号に掲げるものを除く。) | ○ |
| 七 | 口腔咽喉薬(第二十号に掲げるものを除く。) | ○ |
| 八 | コンタクトレンズ装着薬 | ○ |
| 九 | 殺菌消毒薬(第十五号に掲げるものを除く。) | ○ |
| 十 | しもやけ・あかぎれ用薬(第二十四号に掲げるものを除く。) | ○ |
| 十一 | 瀉下薬 | ○ |
| 十二 | 消化薬(第二十七号に掲げるものを除く。) | ○ |
| 十三 | 滋養強壮、虚弱体質の改善及び栄養補給が目的とされている物 | ○ |
| 十四 | 生薬を主たる有効成分とする保健薬 | ○ |
| 十五 | すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面等の消毒又は保護に使用されることが目的とされている物 | |
| 十六 | 整腸薬(第二十七号に掲げるものを除く。) | ○ |
| 十七 | 染毛剤 | |
| 十八 | ソフトコンタクトレンズ用消毒剤 | |
| 十九 | 肉体疲労時、中高年期等のビタミン又はカルシウムの補給が目的とされている物 | ○ |
| 二十 | のどの不快感を改善することが目的とされている物 | ○ |
| 二十一 | パーマネント・ウェーブ用剤 | |
| 二十二 | 鼻づまり改善薬(外用剤に限る。) | ○ |
| 二十三 | ビタミンを含有する保健薬(第十三号及び第十九号に掲げるものを除く。) | ○ |
| 二十四 | ひび、あかぎれ、あせも、ただれ、うおのめ、たこ、手足のあれ、かさつき等を改善することが目的とされている物 | |
| 二十五 | 医薬品医療機器等法第二条第三項に規定する使用目的のほかに、にきび、肌荒れ、かぶれ、しもやけ等の防止又は皮膚若しくは口腔の殺菌消毒に使用されることも併せて目的とされている物 | |
| 二十六 | 浴用剤 | |
| 二十七 | 第六号、第十二号又は第十六号に掲げる物のうち、いずれか二以上に該当するもの | ○ |
昭和36年厚生省告示第14号(改正:平成21年厚労省告示第25号) PDF:11KB
上記表の右欄に○があるものは、医薬品医療機器等法施行令第二十条第二項の規定に基づき、製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医薬部外品(いわゆるGMP適用医薬部外品)
平成16年12月24日厚生労働省告示第432号 PDF:8KB
医薬部外品製造販売承認
医薬部外品の製造販売行う際には、品目ごとに厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。(法第14条)
”承認”とは、製造販売される製品の品質、有効性及び安全性に関する事項について適当か否か判断され、厚生労働大臣が与えるものです。
ただし、次の場合は承認が与えられません。
1 承認申請者が、製造販売業許可を受けていないとき
2 申請品目の製品を製造する製造所が、製造業許可、認定又は登録を受けていないとき
3 申請に係る医薬部外品の名称、成分、分量、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能、副作用その他の品質、有効性及び安全性の審査の結果、その物が次のイからハまでのいずれかに該当するとき
イ 申請に係る医薬部外品がその申請に係る効能、効果又は性能を有すると認められないとき。
ロ 申請に係る医薬部外品がその効能、効果又は性能に比して著しく有害な作用を有することにより、医薬部外品として使用価値がないと認められるとき
ハ イ又はロに掲げる場合のほか、医薬部外品として不適当なものとして厚生労働省令に定める場合に該当するとき。
4 申請に係る医薬部外品が政令で定めるものであるときは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合していると認められないとき。
お問い合わせ
このページの担当は健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課医薬品審査担当です。