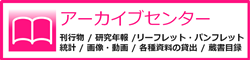沿革
昭和45年4月、都民の食生活の安全確保を図るため、全国に先駆けて食品機動監視班が設置されました。
当時は、食品添加物の安全性が社会的に問題視され始めた時期でした。また、乳児用ミルクのヒ素中毒事件や食用油に混入した有害物質(PCB等)による食品公害事件等、食品への不安がうっ積した時代でした。
これらのことから、食品衛生に関する諸問題を解決するために、機動力を持ち、保健所の管轄区域を越えて緊急的かつ広域的な監視を行う組織として設置されたのが食品機動監視班です。
以後、食品衛生行政を取り巻く環境の変化に応じて以下のような組織改変を行い、現在は食品監視第一課及び第二課の2課体制で、高度な専門性や機動性を生かして広域的な監視指導を実施し、都民の食に対する安全と安心に寄与しています。
| 年月 | 組織体制 | 食品衛生行政を取り巻く環境 |
|
昭和45年4月 |
食品機動監視班設置 ・1個班あたり食品衛生監視員3名、運転手1名 ・23区内の保健所7ヶ所、多摩地区の保健所3ヶ所の計10所に分駐 |
食品添加物に対する安全性が問題視され、食品に起因する事故も多発 |
|
昭和50年4月 |
都の食品衛生監視員の身分に加え、特別区の食品衛生監視員の身分を併任 |
特別区への保健所移管に伴い、都と区の役割分担を定めた「広域監視実施要綱」を施行 |
| 昭和54年3月 |
併任解除 |
|
| 昭和56年4月 |
業務見直し ・1個班あたり食品衛生監視員2名、運転手1名 ・特別区内の保健所7ヶ所、多摩地区の保健所3ヶ所の計10所に分駐 |
特別区の検査体制等整備に伴い、都による補完的業務を終了 |
| 昭和62年6月 |
業務の集中化による組織改変 ・特別区内の7個班を3分室に統合 ・3分室及び多摩地区の保健所3か所に副主幹を配置 |
輸入食品の増大、食品製造技術の高度化 |
| 平成2年4月 |
輸入食品監視班設置 ・1個班食品衛生監視員3名 |
平成元年9月「食品安全条例制定」の直接請求 |
| 平成2年8月 |
食品環境指導センター設置 ・食品環境指導センター(特別区内):食品機動監視班7個班、輸入食品監視班1個班 ・食品環境指導センター多摩支所(多摩地区):食品機動監視班3個班 |
有害食品等をより迅速に排除し、輸入食品を流通の上流段階でチェックする専門監視を実施 |
| 平成10年4月 |
ハサップ指導係を設置 ・1個班食品衛生監視員3名 |
平成7年の食品衛生法改正で、「総合衛生管理製造過程」の承認制度を導入 |
| 平成14年4月 |
東京都食品指導センターに改称 |
JAS法に基づく監視権限の付与 |
| 平成15年4月 |
健康安全研究センター設置 ・広域監視部食品監視指導課(特別区内):食品機動監視班6個班、輸入食品監視班2個班 ・多摩支所広域監視課(多摩地区):食品機動監視班2個班、市場監視班4個班、ハサップ指導班1個班 |
危害発生未然防止型の安全対策実現のため、食と薬に係る監視・検査・研究体制の一元化 |
| 平成21年4月 |
業務見直し ・輸入食品監視班3個班 |
|
|
平成24年4月 |
組織改正 ・広域監視部食品監視指導課→広域監視部食品監視第一課 ・食品監視第一課内に食品表示監視班設置(2個班) ・多摩支所広域監視課→広域菅支部食品監視第二課 |
平成23年7月、米トレ法に基づく産地情報の伝達制度開始
|
|
平成25年4月 |
業務見直し ・輸入食品監視班2個班 |
問い合わせ
このページは、広域監視部食品監視部門が担当しています。