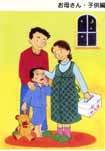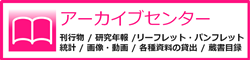過去に作成したパンフレットです。
内容に現在の制度とは異なる部分がありますので、ご注意ください。
お母さん・子供
Q3授乳中の薬の影響
Q6小児とアスピリン
家庭
Q13目薬の共用
Q14着色された薬
Q15薬の使用期限
Q16薬の保管方法
ミニ知識
ご存じですか
Q1 妊娠中の薬の服用はよくないと聞いていますが本当ですか。
 妊娠中の薬の服用は、妊婦自身への影響と、胎児への影響とがあり、特に胎児に関しては、重大な影響を及ぼす場合があります。
妊娠中の薬の服用は、妊婦自身への影響と、胎児への影響とがあり、特に胎児に関しては、重大な影響を及ぼす場合があります。
妊娠3か月くらいまでは、おなかの赤ちゃんの形や臓器が作られる期間で、薬の影響をいちばん受けやすい時なのです。
また、この時期を過ぎても、出産までは多少とも影響があると考えた方がよいでしょう。
もし、妊娠中に病気になったら、ひとりで悩まないで、かかりつけの医師に相談することをおすすめします。医師は、薬が必要かどうか、必要ならどの薬が安全かを十分考えたうえで薬を投与してくれるからです。
なお、医師から服用するように言われた場合は、自分の判断で止めたり量を減らしたりせず、その薬をきちんと飲んでください。
Q2 妊娠したのですが、ビタミン剤、カルシウム剤、鉄剤などの保健薬の服用は必要ですか。
妊娠中はビタミン、タンパク質、カルシウム、鉄をはじめ、必要な栄養はすべてお母さんの血液からおなかの赤ちゃんに補給されます。そのため、特に質のよいバランスのとれた食事をとることが大切です。
このような食事をとっていれば、医師から服用することを指示された場合以外は、薬や健康食品による栄養の補給は特には必要ないでしょう。
ところで、最近の私達の食生活をみますと、極端なダイエットや偏った食事のために貧血になったり、逆にカロリーのとり過ぎや運動不足による太り過ぎが増える傾向にあります。
妊娠中の太り過ぎは、体の働きに異常をひき起こし、さまざまな病気の原因となるおそれがありますので特に注意しましょう。
Q3 授乳中ですが、薬を服用した場合に赤ちゃんへの影響が心配です。
お母さんが飲んだ薬は、ほとんどの場合、多少なりとも母乳中に分泌されます。そこで、お母さんが飲んだ薬が、母乳を通じて赤ちゃんに移り、中毒やアレルギー、発育障害などの影響を与える場合があります。
授乳中に病気になった場合は、自分の判断で薬を飲むことは避け、医師の診察を受けてから薬を飲むようにしましょう。

私、くすりをのんでしまったけど...
Q4 赤ちゃんに、上手に薬を飲ませるにはどうしたらよいですか。
1 シロップ剤の飲ませ方
容器をよく振り、小さなスプーンで少量ずつ赤ちゃんの舌にのせ飲ませます。薬をスプーンに出し過ぎた場合は、容器に戻さず捨ててください。
2 粉薬の飲ませ方
1回量を少量の湯ざましか砂糖水で練り、スプーンで少量ずつ与えるか、よく洗った指に付けて口に含ませます。苦みのある薬の場合は、ほおの内側や上あごにすり付け、その後、水やジュースをあげるとよいでしょう。
<注意したいこと>
ほ乳ビンのミルクに薬を混ぜて飲ませると、ミルクの味が変わったことでミルク嫌いになることがあります。また、ミルクを飲み残すと、必要な薬の量を飲まなかったことになるので注意しましょう。

Q5 小児に薬を使用するに当たって注意することはどんなことですか。
小児に薬を服用させるときは、「症状に適した効能か。」、「服用量が年齢、体重に見合っているか。」、「服用しても危険のない剤形か。」などに注意を払う必要があります。
買い置きの薬の中には、小児向けの効能がない、剤形が大き過ぎて小児の服用が困難、などの理由で、効能書に小児への用法、用量の記載のないものがあります。この場合は、服用を見合わせ、薬局、薬店の薬剤師などに相談しましょう。
カプセル剤、錠剤、丸剤などは、大人にとっては飲みやすい剤形ですが、1から2歳の幼児では誤って気管内につまらせてしまうなど危険な場合があります。できるだけ、小児用としてつくられたシロップ剤などの液剤や、服用による危険性のない坐剤を用いた方がよいでしょう。
また、つぶして与えることも薬によっては大変苦みが強くなり、さらに薬に対する拒否反応を増すことになるのでやめましょう。

Q6 小児にアスピリンを飲ませない方がよいと聞きましたが本当ですか。
アスピリンは、解熱鎮痛薬として昔からよく使われている薬剤で、安全性の高い薬のひとつです。
しかし、小児が水痘(水ぼうそう)やインフルエンザなどのウイルス性疾患にかかっている場合にアスピリン等のサリチル酸系薬剤を服用すると、「ライ症候群」という病気にかかりやすくなるおそれがあります。
現在、アスピリン系サリチル酸製剤は小児に使用しないことになり、市販の小児用の解熱鎮痛剤、かぜ薬には、アスピリン以外のアセトアミノフェン、エテンザミドなどの成分が使用されています。
小児が発熱したときに、安易にアスピリンを使うことは控え、医師や薬剤師に相談しましょう。
| ミニ知識 「ライ症候群」とは |
主に小児において水痘やインフルエンザなどのウイルス性疾患にかかった後、激しいおう吐、意識障害、けいれんと肝機能障害などの症状が一週間位の間に現れる疾患です。
極めてまれにしか起こらないものですが、死亡率が高いので早めの診断と治療が必要です。
Q7 子供が誤って薬を飲んだときは、どうしたらよいですか。
 薬には、糖衣錠やシロップ剤のように甘くしたものや、色や形からお菓子と間違えられやすいものがあります。
薬には、糖衣錠やシロップ剤のように甘くしたものや、色や形からお菓子と間違えられやすいものがあります。
なめたり、口に含んだり、少量飲み込んだ程度で、すべての薬が中毒症状を現わすわけではありません。
しかし、大量に飲み込んだ場合や、少量でも作用の強い薬や、吸収までの時間が短い薬の場合は、水か牛乳を飲ませ、吐かせるなど応急の処置が必要になります。
慌てずに、飲み込んだ薬の種類や子供の状態を冷静に判断して行動してください。
何の薬かわからない場合や心配な場合は、直ちに薬を袋ごと持参して医師の診察を受けましょう。
医師からは次のようなことを聞かれますので、慌てずしっかり答えてください。
1 いつ頃
2 何の薬か又はどの薬か
3 どの位の量を飲んだか
4 何か処置をしたか
なによりも大切なことは、薬は子供の手の届かない場所に保管することです。
| ご存知ですか? 中毒110番 急性中毒に関する緊急の電話相談を受けています。 |
| 公益財団法人日本中毒情報センター | ||
| つくば中毒110番 | 電話番号 029−852−9999 | 9時から21時 |
| 大阪中毒110番 | 電話番号 072−727−2499 | 24時間対応 |
Q8 子供がうがい中にうがい薬を少し飲み込んでしまいましたが、大丈夫ですか。
大人でもうがい中には少し飲み込んでしまうことがあります。まして子供の場合には、飲み込まずに上手にうがいをすることはなかなか難しいでしょう。うがい薬は比較的安全性が高い薬剤ですから、少量飲み込んだ程度では、問題ありません。しかし、水に溶かしたり薄めたり、定められた用法、用量に従って使用するよう、大人が指導することが大切です。
Q9 蚊取線香や蚊取マットを赤ちゃんのいる部屋で使用してもよいですか。
 蚊取線香や蚊取マット(リキッドタイプを含む。)の多くは、除虫菊に含まれるピレトリンや合成ピレトリンなどのピレスロイド系殺虫剤を主な成分としています。
蚊取線香や蚊取マット(リキッドタイプを含む。)の多くは、除虫菊に含まれるピレトリンや合成ピレトリンなどのピレスロイド系殺虫剤を主な成分としています。
これらの薬剤は、人に対する安全性が高く、赤ちゃんのいる部屋で使用しても、特に問題はないと思われます。
しかし、部屋を締め切って使用すると、眼やのどを刺激することがあるので、網戸を利用するなど、適度な換気が必要です。
また、赤ちゃんが手で触れたり、口に入れたりして思わぬ事故の原因になることがあります。赤ちゃんの手の届かない安全な場所に置くなど、お母さんの心配りが必要です。
Q10 薬を買う時には、どんなことに気をつけたらよいですか。
 薬は、使う人の症状や体質によって、その選び方も少しずつ違ってきます。薬を買う際には、病気の症状や体質、また誰が使うのかを、薬局、薬店の薬剤師など専門家によく相談することが必要です。
薬は、使う人の症状や体質によって、その選び方も少しずつ違ってきます。薬を買う際には、病気の症状や体質、また誰が使うのかを、薬局、薬店の薬剤師など専門家によく相談することが必要です。
特に、妊娠中の人、授乳中の人、薬物アレルギーのある人、慢性疾患のある人などは、必ずそのことを申し出るようにしましょう。
また、薬には、薬物相互作用といって、2種類以上の薬を一緒に飲むと効き目が弱くなったり、逆に強くなったりするものや、思わぬ副作用が現れたりするものがあります。
病院や診療所から出された薬を飲んでいる人は、買う前によく相談するように心がけましょう。
| ミニ知識 一般用医薬品と医療用医薬品 |
一般用医薬品とは、薬局、薬店で売られている薬や、置き薬のことで、薬剤師・登録販売者(※)などから提供された情報に基づき、自己の判断で購入し使用できます。つまりセルフメディケーション(自己治療)のための薬です。
一方、医療用医薬品とは、病院や診療所で医師、歯科医師の診察結果に基づいて使用されたり、医師、歯科医師の処方せんによって、薬局で調剤されたりする薬のことです。(※)登録販売者とは、一般用医薬品(市販薬)の販売をする、薬剤師と違う新たな専門家です。
Q11 最近、セルフメディケーションという言葉をよく耳にしますが、どんなことですか。
セルフメディケーション(自己治療)とは、カゼのひき始めなどの軽い症状や軽いケガなどの場合に、医師の診療を受けず自分の判断で市販の薬によって治療することです。
つまり、病気やケガの原因が明らかで、過去に経験し、症状が軽いものは比較的自分の判断での治療が可能なものです。
しかし、次のような症状などの時は、医師の診察を受けるようにしましょう。
1 頭痛、吐き気、下痢、発熱などの症状が複合して現れたとき
2 高熱が続き、薬を飲んでも熱が下がらないとき
3 脈が速かったり、乱れたりしたとき
4 腹痛がなかなか止まらないとき
5 その他、症状が強いとき
特に、赤ちゃんは大人と同じに考えないで、早いうちにかかりつけの医師に診てもらいましょう。
| ミニ知識 錠剤、カプセル剤のいろいろ |
| 腸溶(ちょうよう)錠、カプセル | 胃で溶けず腸で溶けるように皮膜した製剤 |
| 徐放(じょほう)錠、カプセル | 有効成分が徐々に溶けだすよう工夫した薬剤 |
| 重層(じゅうそう)錠 | 溶解性の異なる複数の成分を層状にした薬剤 |
Q12 錠剤やカプセル剤などは、くだいたりカプセルの中身を出したりして飲んでもよいですか。
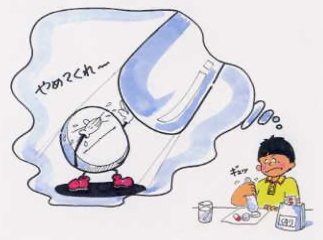 錠剤やカプセル剤は、飲む量が正確にとれ、持ち運びに便利、さらに飲みやすいなどの特徴があります。
錠剤やカプセル剤は、飲む量が正確にとれ、持ち運びに便利、さらに飲みやすいなどの特徴があります。
また、クスリの中にはそれ自体が苦かったり、においや刺激の強いものもあります。このような薬を飲みやすくするために、錠剤の表面を甘くしたり、カプセルの中にとじ込めたりしています。
このほか、薬が腸で吸収されるよう工夫したものや、長時間にわたって効果を持続させるため、成分が少しずつ溶け出すように工夫したものもあります。ですから薬を飲むときは、むやみにくだいたり、カプセルの中身を取り出したり、かんで小さくしたりすることは避けましょう。
ただ、錠剤のなかには中央に割れ目の入っているものがあります。これは、割って飲むことを考えて作られていますので、このような錠剤は必要に応じて割って飲むことができます。
Q13 家族と目薬を共有してもよいですか。
 目薬は、プールの後や疲れ目、目の充血、目のかすみなどの症状に使用され、家庭ではよく使われる薬の一つです。
目薬は、プールの後や疲れ目、目の充血、目のかすみなどの症状に使用され、家庭ではよく使われる薬の一つです。
目は、からだの中でも特にデリケートな部分ですので、目薬は細菌などによって汚染されないよう、滅菌したり保存剤が添加されたりしています。
しかし、使う時に容器の先がまぶたやまつ毛などに触れて目ヤニや雑菌が薬液に入り、汚染されることがあります。
家族のうちの一人でも目の感染症にかかっていた場合、その目薬を別の人が使えば、感染することが十分考えられます。
ですから、目薬は家族のなかでも共用せずに、各人で使い分けることをおすすめします。
<注意>薬液のにごりは、目薬に何らかの変化が生じたことを示す一つの目安になります。
Q14 いろいろに着色された薬を見かけますが、安全ですか。

薬には、錠剤、カプセル剤をはじめ同じ形のものが数多くあります。それらを、とり違えずに、間違いなく飲むことが、薬を安全に使うための第一歩と考えられます。
もし、ほかの薬を誤って飲んだりすれば、重大な事故を招く恐れがあります。そこで薬は、着色したり、識別コードを刻印するなどして区別しやすいように工夫されているのです。
しかし、着色するためにどんなものを使ってもよいわけではありません。医薬品に使用できる色素は、医薬品の製造、販売などを規制している医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)によって決められています。そのため、決められた色素以外のものを使った医薬品は、製造、販売することが禁止されています。つまり、人体にとって安全であると判断された色素のみが使われているのです。
Q15 薬によって、使用期限や有効期限が表示されているものと、表示されていないものとがありますがなぜですか。
 薬の外箱に、「使用期限2001.10.」などと書かれているのを目にします。これは、メーカーが一定の試験を行い、その薬の性状や品質を保証するために決めた期限のことです。
薬の外箱に、「使用期限2001.10.」などと書かれているのを目にします。これは、メーカーが一定の試験を行い、その薬の性状や品質を保証するために決めた期限のことです。
医薬品医療機器等法では、メーカーに対して、性状や品質が不安定なものについては、使用期限を表示するよう義務付けています。
性状や品質が3年以上安定なものには、使用期限を記載する義務はありませんが、メーカーが自主的に使用期限を記載しているケースが多いようです。使用期限は余裕をもって決めてありますので、期限切れだからといって、薬の品質が急に落ちるというわけではありません。
しかし、薬の品質は保管方法や場所にも大きく左右されますので、期限の切れた薬を使うのは避けた方がよいでしょう。
また、抗生物質やワクチンなど厚生労働大臣が特別に一定の基準を定めたものもあります。これには、有効期限という言葉が使われています。有効期限も使用期限と同じ意味あいと考えてよいでしょう。
Q16 薬を保管するときは、どんな注意が必要ですか。
薬の保管方法で最も大切なことは、直射日光や湿気を避け、涼しい乾燥した場所に保管することです。窓際や車の中などはよくありません。また、目薬や坐薬などは、冷蔵庫など冷たい所に保管するとよいでしょう。
<次のことに注意して保管しましょう>

いつも決まった場所に
薬は救急箱に入れ、家族がすぐに使えるよういつも決まった場所に置いておきましょう。
子供の手の届かない所に
薬には甘くて飲みやすいものもあります。そこで、子供のいる家庭などでは、子供の手の届かない安全な場所に保管しましょう。
薬の詰めかえはやめましょう
薬を他の容器に移しかえたりすると、後で何の薬かわからなくなり危険です。容器の種類などによっては保存状態が悪くなり、薬の効き目がなくなったりすることもあります。
また、お菓子の空き缶に薬を入れておくと、子供が間違って食べることにもなりかねません。
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 食品医薬品情報担当 です。