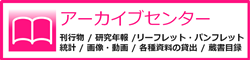「健康食品」を利用するために必要な心構え
「健康食品」を利用するための12か条 を紹介します。
▶詳細はこちらから。
「健康食品」を正しく理解しましょう
1 |
「健康食品」は、素材の種類や食べ方(加工)が一般の食品と異なることがあります。そのため、安全性については一般の食品よりも慎重に考えるようにしましょう。 |
| 2 | 「健康食品」は、あくまで食生活における補助的なものと考えましょう。 |
| 3 | 「健康食品」は、病気や体の不調を治すものではないことを意識しましょう。 |
「健康食品」の利用前にご確認ください
4 |
「健康食品」を利用する前に、普段の食生活で、本当に補給する必要のある栄養成分があるか、考えてみてください。 |
| 5 |
健康に役立つ食品機能を紹介する「健康情報」は、そのまま受け入れるのではなく、 科学的な視点に基づく判断を行ったうえで参考にしてください。 |
| 6 | 製品を選ぶ際には、表示や広告をよく確認してください。 |
| 7 |
個人輸入やインターネットオークションを利用する際には、製品に関する情報の確認をしてください。 |
| 8 | 保健機能食品制度について理解を深めることは、「健康食品」を利用するうえで重要なことです。 |
| 9 | 特定の成分を過剰に摂取しないように気をつけてください。 |
| 10 | 「健康食品」の利用期間や量などについて記録をとってください。 |
医療機関への相談
11 |
体調不良を感じたら、すぐに利用をやめて医療機関を受診してください。 |
| 12 | 治療を受けている人が「健康食品」を利用する場合には、医師や薬剤師などに相談してください。 |
参考
▶バランスのよい食事って?(とうきょう健康ステーションへリンク)
▶注意が必要な健康食品(健康食品ナビ内の別のページへリンク)
▶パンフレット「健康食品ウソ? ホント?」(健康食品ナビ内の別のページへリンク)
| このページの管理は、 東京都健康安全研究センター企画調整部健康危機管理情報課食品医薬品情報担当です。 電話:03-3363-3472(直通) メールアドレス:S1153803※section.metro.tokyo.jp ※を@に置き換えてメールをお送りください。 |