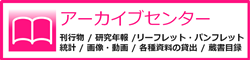*記載内容
| タイトル |
|---|
| 和文要旨 |
| キーワード |
総説
|
梅毒トレポネーマの核酸検出法及び核酸型別法 |
|---|
|
Treponema pallidum subsp. pallidum (梅毒トレポネーマ)を起因菌とする梅毒は,近年,東京都を含む全国で報告数の顕著な増加がみられている.従来より梅毒の診断は血清を用いた抗体検査が行われてきた.一方で,陽性であっても被験者から梅毒菌体を補足するのは難しく,核酸検出法を含めた抗原検査法は一般的ではなかった.しかしながら,梅毒の届出基準には検査方法としてPCR検査等による病原体の検出が挙げられており,有症状の初期梅毒の診断において有効となる場合がある.また,梅毒トレポネーマの核酸型別法からは,特定の地域での感染拡大の主流となっている型,集団間の関係性や伝播の様態や,薬剤耐性変異の有無といった疫学的な知見が得られることが知られている.本報では,梅毒トレポネーマの核酸検出法の実験室的手法や市販試薬及び核酸型別法についての概要を紹介する. |
|
梅毒,Treponema pallidum,核酸検出法,核酸型別法,ECDCT,SBMT |
事業報告
| 健康危機管理に関連する微生物の分子疫学解析と検査法の開発に関する研究 |
|---|
|
2021~2023年度に東京都健康安全研究センターで実施した重点研究「健康危機管理に関連する微生物の分子疫学解析と検査法の開発に関する研究」の概要について報告する.本研究では,新型コロナウイルス,多剤耐性菌,結核菌,真菌,腸管出血性大腸菌,芽胞菌やデータベースを対象とし,次世代シーケンサー,リアルタイムPCR,MALDI-TOF MS等の新しい手法を駆使して病原体を網羅的に解析した.さらに,実際の検査への導入を図るとともに,行政への貢献(東京iCDCへの報告を含む)や都民へ情報発信を行った.本研究で得られた膨大な成果は,関連学会や論文等で報告しており,今後,全国の地方衛生研究所等における食中毒や感染症等の健康危機対策への応用が可能と考えられる. |
|
健康危機管理,次世代シーケンサー,リアルタイムPCR,MALDI-TOF MS,データベース |
| ワンヘルスアプローチに基づく抗微生物薬と薬剤耐性微生物の実態把握に関する研究 |
|---|
|
令和3–5年度に実施した重点研究「ワンヘルスアプローチに基づく抗微生物薬と薬剤耐性微生物の実態把握に関する研究」の概要を報告する.本研究は,世界的に人類の健康への大きな脅威となっている薬剤耐性(AMR)の対策への一環として,コンパニオンアニマル,食品,農産,畜産及び環境における抗微生物薬と薬剤耐性微生物の存在実態の両面からアプローチすることを目的とした.5つの個別課題を進めたところ,次の成果を得た.薬剤耐性菌の存在実態に関しては,基質特異性拡張型βラクタマーゼ産生大腸菌株の分子疫学的解析より,ヒト流行株と近縁の株がイヌ,ネコ,河川水よりを検出することを示した.これにより,ヒトから排出された耐性菌が,ペットや河川へ伝播するといった関連性が窺えた.一方,食品由来株は,遺伝子型が異なっていた.また,耐性獲得や伝播の仕方について一考察を得た.抗微生物薬の実態については,AMRを獲得するよりも低い濃度の残留の有無を判定し,かつ精確にその量を測定出来るようにすることを試みた.畜産食品中の高極性抗微生物薬,農産食品及び環境水中農業用殺菌剤に対し,各々の試料に適した高感度かつ高精度な分析法開発を行った.開発法の応用として,食品分野では日常検査への導入を試み,環境分野では浄水処理の挙動の解明を行った.成果の発信により,WHOが提唱するワンヘルスアプローチに基づく薬剤耐性対策の強化の一助となった. |
|
薬剤耐性,ワンヘルスアプローチ,ESBL産生大腸菌,高極性抗微生物薬,農業用殺菌剤,コンパニオンアニマル,畜産食品,農産食品,環境水,浄水処理,ゲノム解析,LC-MS/MS |
| 危険ドラッグ等に含まれる薬物の科学分析法及び生体影響評価法に関する研究 |
|---|
|
本研究では、危険ドラッグに含まれる新規の精神作用を示す薬物の科学的な分析法と生体影響評価手法について,4研究課題を設定し実施した。(1)危険ドラッグに含有される薬物の迅速探索法に関する研究では,LC-Tribrid/Orbitrapを用いたNBOMe等と称されるフェネチルアミン系薬物のスクリーニング分析法を開発し,紙片状危険ドラッグに適用した.(2)向精神作用が疑われる成分を含有する植物を混入させた危険ドラッグ製品や,多種類のカンナビジオール製品の流通実態に対し,それぞれの特性に応じた試料前処理法及び機器分析法について検討した.また,分子生物学的手法を用いた植物同定法を導入した.(3)世界的に乱用されている非フェンタニル系合成オピオイドであるNitazene類の精神依存性を,マウスを用いた実験により明らかにした.また,脱離エレクトロスプレーイオン化-質量分析イメージング法(DESI-MSI)を用いて,Nitazene類のマウス脳内分布について解析した.(4)ラットの肝臓や腎臓に傷害を起こしたフェンタニル系薬物の毒性について検討するため,HEK293細胞を用いて2種類のμオピオイド受容体(MOR)シグナル応答を調べたところ,両方のシグナル応答とも肝臓や腎臓に対する毒性と相関性があることが示唆された.また,これらの薬物の主要な代謝物と考えられる脱フェネチル化体は,MORシグナル応答を示さず,肝臓や腎臓の傷害への関与は低いことが推察された. |
|
危険ドラッグ,LC-Tribrid/Orbitrap,NBOMe,25I-NBOH,マオウ属植物,カンナビジオール,nitazene,conditioned place preference,in vivo microdialysis,desorption electrospray ionization mass spectrometry imaging (DESI-MSI) ,フェンタニル系薬物,HEK293細胞,μオピオイド受容体(MOR),脱フェネチル化体 |
論文Ⅰ 感染症等に関する調査研究
|
リアルタイムPCR法によるパレコウイルスA検出法の開発及び検出状況 (2022年度から2023年度) |
|---|
|
リアルタイムPCR法によるパレコウイルスA(PeV-A)遺伝子検査法を新たに構築した.本検査法を用いて,2022年度,2023年度の発生動向調査及び積極的疫学調査で搬入された634例を対象にPeV-Aの検索を実施した.その結果,39例からPeV-A遺伝子を検出した.検出されたPeV-Aは,A1型13例,A3型18例,A4型1例,A6型7例であった.PeV-Aが検出された年齢は,0歳から6歳であり,呼吸器感染症や発疹症から検出された.PeV-A が単独で検出された疾患は,手足口病,突発性発疹,不明発疹,ヘルパンギーナ,麻しん・風しん,伝染性紅斑,流行性耳下腺炎であったが,多くの検体でPeV-A以外のウイルスとの重複感染も確認された.PeV-Aが単独で検出された疾患は臨床診断名が発疹症であることが多い傾向にあった. |
|
パレコウイルスA,PeV-A ,不明発疹症,リアルタイムPCR法,手足口病,突発性発疹,不明発疹,ヘルパンギーナ,麻しん・風しん,伝染性紅斑,流行性耳下腺炎 |
| 地方衛生研究所における次世代シークエンサーの利用と課題 |
|---|
|
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を契機に,次世代シークエンサー(NGS)が全国の地方衛生研究所(地衛研)で配備され,新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株解析等で活用されている.NGSのそれ以外の具体的な利用法としては,臨床検体の網羅的な病原体解析,病原体の詳細な遺伝子解析等が想定される.また,地衛研を取り巻く状況として,感染症予防計画等を踏まえた健康危機対処計画が策定された.微生物分野における健康危機事例発生時の質の高い病原体検査は地衛研において必須となり,従来の検査法に加え,NGSの効果的な活用を標準化していかなければならない.一方で,NGSに関係するインフラ,技術,予算および人材育成面での課題は山積している.特に,網羅的解析等に係るソフトウェア,パルスフィールドゲル電気泳動法としての代替法としての利用,集積したゲノム情報の活用等,地衛研として解決すべき課題は多い.本稿では,地衛研におけるNGS解析法の使用法を紹介するとともに,地衛研が抱える課題について考えてみたい. |
|
次世代シークエンサー,地方衛生研究所,利用,解析 |
|
食品からの腸管出血性大腸菌ベロ毒素(VT)遺伝子の抽出法及び検出法の検討 |
|---|
|
一般食品からの腸管出血性大腸菌の検査では,厚生労働省通知に準じて,ベロ毒素(VT)遺伝子を対象としたスクリーニング検査を実施している.しかし,脂肪,多糖類など食品中のPCR反応阻害物質が遺伝子増幅を妨げる場合が想定される.そこで,食品成分によりPCR反応が阻害されやすい加工食品(チョコレートを含む食品,褐藻類を含む食品,ベリー類,菓子類及びソース類)について,6種類の遺伝子抽出法と2種類のリアルタイムPCR Master Mixを用いてPCR阻害物質の影響について比較した.その結果,チョコレートを含む食品については,アルカリ熱抽出法で抽出した場合,リアルタイムPCR Master Mixの種類に関わらずPCR反応が阻害された.一方で,その他の食品については,抽出法及びリアルタイムPCR Master Mixの組み合わせによってPCR反応に違いが生じることが確認された.そのため,一般食品からの腸管出血性大腸菌検査では,特に通知法の同等品を用いる場合には,抽出法やリアルタイムPCR Master Mixの特性を踏まえて適した方法を選択する必要があると考えられる. |
| 腸管出血性大腸菌,ベロ毒素,DNA抽出法,PCR反応阻害物質 |
|
東京都公的HIV検査の動向とHIV陽性検体の薬剤耐性遺伝子解析 (2019年1月~2024年3月) |
|---|
|
2019年1月から2024年3月までに東京都公的HIV検査機関で採血され,東京都健康安全研究センターで実施したHIV検査数の推移を調べた.新型コロナウイルス感染症流行下の2020年,2021年は検査数が著しく減少したが,2023年には2019年と同程度の水準にまで回復した.また,都内で流行しているHIVを調査することを目的に,東京都健康安全研究センターで実施したHIV検査において,HIV-1陽性となった検体を用いて遺伝子解析を行い,サブタイプ型別ならびに薬剤耐性関連変異を検索した.HIV-1陽性492件のうち,遺伝子解析が可能であった273件のサブタイプ型別を行った結果,サブタイプBが約75%であり,次いでCRF01_AE が約15%を占めていた.薬剤耐性関連変異については,プロテアーゼ領域および逆転写酵素領域の変異が認められ,また,毎年T215-revertantも検出されていた.都内でのHIV流行株は年により変化が見られることから,HIV流行状況の把握のためにも新規HIV陽性検体に対してサブタイプや薬剤耐性関連変異について調査することが重要である. |
| ヒト免疫不全ウイルス,後天性免疫不全症候群,HIV検査,薬剤耐性関連変異 |
| 都内河川水からのEscherichia albertii の検出および分離菌株の性状 |
|---|
|
Escherichia albertii は2003年に報告された新興下痢症起因菌であり,分離法や生息環境については未だ不明確な点が多い.今回,東京都内の河川水におけるE. albertii の検出を試み,また分離菌株について薬剤感受性試験や病原遺伝子等の調査を行った.2022~2023年度に採水した河川水88検体について,リアルタイムPCRを用いたスクリーニング試験を行ったところ,58検体(65.9%)がE. albertii 特異的遺伝子(EAKF1_ch4033)陽性となり,うち10検体からE. albertii が分離された.河川水検体からのE. albertii 分離においては,mEC培地による増菌培養に比べ,その後にNCT-mTSBでの二次増菌培養を加えることで菌株分離が容易になった.また,糖分解性を利用する培地(XR-Mac)に加え,酵素基質培地(XM-G)の併用が有用と考えられた.分離菌株の薬剤感受性試験では,10株すべてが供試した17薬剤に感受性を示し,病原遺伝子等eae,lysP,mdhおよびcdtBを保有していた.また,PFGE法による解析結果から,一部の株は遺伝子学的に近縁の可能性が示唆された. |
|
河川水,Escherichia albertii,XR-MacConkey agar,XM-G寒天培地,リアルタイムPCR |
| 東京都内に流通する食肉の細菌学的実態調査(2021~2023年度) |
|---|
|
2021~2023年度に都内に流通する国産及び輸入食肉の細菌検査を実施した.検査項目は衛生指標菌として一般生菌数,大腸菌群,黄色ブドウ球菌及びウエルシュ菌,食中毒菌起因菌として腸管出血性大腸菌,サルモネラ,リステリア・モノサイトゲネス,病原エルシニア及びカンピロバクターである.453検体について調査した結果,食中毒起因菌では,腸管出血性大腸菌が1.1%,サルモネラが11.0%,リステリア・モノサイトゲネスが15.0%,病原エルシニアが0.7%,カンピロバクターが13.0%から検出された.腸管出血性大腸菌は国産牛肉の他,輸入羊肉や輸入カンガルー肉からも検出された.また,サルモネラ及びカンピロバクターは国産鶏肉の陽性率が高く,リステリア・モノサイトゲネスは輸入鶏肉の陽性率が高かった.さらに,国産豚肉及び国産牛肉から病原エルシニアが検出された.加熱用食肉は様々な食中毒起因菌等により汚染されているため,食肉の各処理段階における衛生管理を適切に実施するとともに,調理従事者や一般消費者に対し加熱不足等に注意するよう啓発していくことが重要である. |
|
食肉,一般生菌数,大腸菌群,腸管出血性大腸菌,サルモネラ,黄色ブドウ球菌,リステリア・モノサイトゲネス,ウエルシュ菌,病原エルシニア,カンピロバクター |
| リアルタイムPCRを用いた髄膜炎菌迅速検査のうがい液検体への応用 |
|---|
|
侵襲性髄膜炎菌感染症は,髄膜炎菌(Neisseria meningitidis)による侵襲性感染症であり,一部は重篤な転帰をとることがある.さらに,本症は急速に症状が進行する場合や,集団事例の発生例も報告されていることから,迅速な検査対応が求められる.本研究では,純培養した3種の髄膜炎菌株を102~108 CFU/mLオーダーで調製したうがい液を混合した疑似検体を用いて,WHOの検査マニュアルに従ったリアルタイムPCR(WHO法)での髄膜炎菌の検出感度を測定し,実際の患者を想定した迅速検査に応用できるかを検証した.その結果,疑似検体中に髄膜炎菌が98,425~118,523 CFU/mL程度存在すれば,リアルタイムPCRで検出可能であることが明らかとなった.一方で,セアーマーチン寒天培地を用いた培養法と比較すると検出感度は約500倍劣っていた.しかし, DNAの抽出やPCRの条件変更など検出感度を高めるための検討の余地は十分にあり,培養法との併用を行うことでWHO法のリアルタイムPCR検出系は髄膜炎菌感染症の迅速検査に応用できることが示唆された. |
|
髄膜炎菌,リアルタイムPCR,うがい液,検出感度 |
|
結核菌検査におけるゲノム解析法に関する検討 |
|---|
|
近年,ベンチトップ型次世代シークエンサー(NGS)が普及し,結核菌の分子疫学調査においても解像度の高いゲノム解析を利用することが期待されている.しかし,標準的なマニュアルに沿えばNGSでは均一なシークエンスデータが得られる一方で,そのデータを用いてゲノム解析を進め,分子疫学調査に利用していく点は検討の段階にある.本研究では,東京都で分離された結核菌株596株についてNGSによって得たシークエンスデータをもとに二種類の解析方法,すなわち,Core Genome Multilocus Sequence Typing(cgMLST)とSingle Nucleotide Polymorphism(SNP)解析について,異なったlocusの数とSNP数を比較した.その結果,cgMLSTにおいて疫学的関連性が強いとされる5 locus違いの株同士のうち98.3%が,同じく疫学的関連性を示すとされる5 SNP以内の関係性となり,同一クラスターの可能性がある最大数である12 locus以内の関係の99.7%はSNPs解析において12 SNPs以内の差となった.以上のことから,一定の疫学的関連性が考えられる株同士においては二法の差はほとんどないと考えられた.ゲノム解析は,一塩基の解像度で菌株の類似性を見ることのできる強力な分子疫学のツールであるが,感染経路の特定には疫学情報の収集が第一であり,これを支援する検査方法としての有用性を継続的に評価していくことが重要である. |
|
結核,分子疫学調査,感染経路,次世代シークエンサー,ゲノム解析 |
|
都内における下水中の新型コロナウイルスモニタリング調査と変異株解析 |
|---|
|
下水中の新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)モニタリングは,COVID-19の流行状況のモニタリングツールの一つとなることが期待されている.今回,2023年5月から2024年5月までに都内水再生センター20カ所(区部13カ所,多摩地域7カ所)で採取された流入下水を対象に,全自動遺伝子検査装置を用いた半定量的SARS-CoV-2検査を実施し,ヒートマップ形式でウイルス量の変化をモニタリングした.その結果,都内定点医療機関あたりの患者数とヒートマップで連動がみられ,流行状況のモニタリングツールとして有用性が示唆された.さらに,下水検体を対象にリアルタイムPCR法による遺伝子変異検出(スパイク蛋白G339D/H)を試みたところ,都内感染者の変異株流行状況を反映した遺伝子変異の変遷が確認された. |
|
下水,新型コロナウイルス,SARS-CoV-2,定量,全自動遺伝子検査装置,ヒートマップ,リアルタイムPCR法 |
|
東京都における胃腸炎ウイルスの検出状況(2022年度~2023年度) |
|---|
|
2022年度から2023年度に東京都健康安全研究センターに食中毒調査,積極的疫学調査,感染症発生動向調査により搬入された検体について胃腸炎起因ウイルスの検査を実施した.その結果,714事例中317事例から胃腸炎起因ウイルス(ノロウイルス:NoV,A群ロタウイルス等)が検出された.内訳はNoVによるものが最も多く,遺伝子型GII.4が大半を占めていた.2023年度は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の5類感染症移行とともに検体搬入数およびウイルス検出数は2022年度と比較して大幅に増加した.また,検出されたNoVの遺伝子型はCOVID-19の流行以前と比較して遺伝子型の多様化が見られた. |
| 食中毒調査,積極的疫学調査,感染症発生動向調査,感染性胃腸炎,ウイルス性食中毒,ノロウイルス,ロタウイルス,サポウイルス,アデノウイルス,アストロウイルス |
|
東京都における新型コロナウイルスの全ゲノム解析 (2023年6月~2024年5月) |
|---|
|
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は2019年12月に中国で初めて確認され,これまでに数多くの新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)変異株が世界中で報告された.2023年の第9波以降に流行したオミクロン株は,BA.2系統内の組み換えにより生じたXBB系統とBA.2系統から派生したBA.2.86系統に大きく分類され,各系統はさらに多くの亜系統に細分化している.東京都では変異株サーベイランスを目的に,SARS-CoV-2の全ゲノム解析を実施してきた.今回,2023年6月1日から2024年5月31日の間に次世代シーケンサー(NGS)により2,733件の解析を実施した結果,2023年11月まではXBB系統のEG.5.1系統が主流であり,2023年12月から2024年5月まではBA.2.86系統のJN.1の亜系統が主流となっていた.都内で検出されたBA.2.86系統の系統樹解析では,JN.1,JN.1.1,JN.1.4のクレードと,KP.2,KP.3およびKP.3.3のクレードの大きく2つに分けることができ,それぞれ海外においても類似株が存在した.以上の結果より,全ゲノム解析で亜系統の分類を時系列的に集計することは,COVID-19の流行状況の詳細な把握に有用と考えられた. |
|
COVID-19,SARS-CoV-2,次世代シーケンサー(NGS),亜系統,系統樹解析 |
|
市販のヒトiPS細胞由来腸管上皮細胞を用いたヒトノロウイルス分離培養方法の検討 |
|---|
|
感染性胃腸炎の主要な原因ウイルスであるヒトノロウイルス(HuNoV)は培養系が確立されていなかったが,近年,ヒトiPS細胞由来腸管上皮細胞(iPS-DIEC)を用いたHuNoV分離培養の成功事例が報告されている.現在,iPS-DIECは国内でも市販されており,iPS細胞の培養や,目的とする細胞への分化処理に関する技術に習熟していなくても,簡便にiPS-DIECを利用することが可能となっている.本研究では,HuNoV陽性の糞便検体を分離材料として,市販のiPS-DIECにHuNoVを接種し,分離培養を試みた.その結果,HuNoV遺伝子型別にみるとRNAコピー数ベースで,最大HuNoV GII.2[P16]は約300倍,GII.3[P12]は約20倍,GII.6[P7]は約700倍,GII.7[P7]は約1,000倍,GII.4[P16]は約3.8倍,GII.17[P17]は約1.5倍に増加した.またHuNoV陽性の糞便検体を,85°Cで5分間加熱して培養が可能か調べたところ,加熱処理により増殖が抑制されることを確認した.以上の結果から,市販のiPS-DIECは,簡便な取り扱いでHuNoVの培養が可能であり,加熱処理等のHuNoV不活化試験等に応用できることが示唆された. |
|
ヒトノロウイルス,ウイルス分離,ヒトiPS細胞由来腸管上皮細胞 |
|
GISAID登録データを用いた東京都内のSARS-CoV-2薬剤耐性変異株の検索(2023年度) |
|---|
|
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)治療薬は,重症患者や重症化リスクのある患者の治療に用いられる一方で,その使用により治療薬の薬理作用から逃避する変異ウイルスの出現が懸念されている.SARS-CoV-2に特有のアミノ酸変異が治療薬に対し強耐性を示すことは現時点では確認されていないが,薬効を減弱させる可能性があるアミノ酸変異が多数報告されている.そこで,国際的なゲノムデータベースであるGlobal Initiative on Sharing Avian Influenza Data(GISAID)登録データを活用し,2023年4月から2024年3月に東京都内で検出されたSARS-CoV-2薬剤耐性変異株について,検出時期別にPANGO系統株との関連性を調査した.その結果,特定の検出時期およびPANGO系統で,薬剤耐性変異株が多数検出された.最も多かった薬剤耐性変異株はnsp12領域に変異を有するG671S株(3,737株)であり,東京都が登録した全4,553株の82.1%を占めた.また,nsp5領域に変異を有するM49L株は8株あり,系統樹解析ではEG.5.1.1,EG.5.1およびHK.3系統(いずれもオミクロン株)内でクラスターを形成したが,クラスター形成株間の疫学的関連性は低いと考えられた. |
|
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2),薬剤耐性,抗ウイルス薬,GISAID,ニルマトレルビル,エンシトレルビル,レムデシビル |
|
東京都無料匿名検査機関におけるHIV検査結果の解析(2019年~2023年) |
|---|
|
2019年から2023年までの5年間に,東京都新宿東口検査・相談室から東京都健康安全研究センターに搬入されたHIV検査検体を対象に検査数ならびに検査結果を集計,解析した.その結果,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)発生以前の2019年の検査数と比較して,2020年~2022年の検査数は一時的に減少したが,2023年には2019年と同程度の検査数に戻っており,都内のHIV検査数にCOVID-19の流行が影響していたことが示唆された.また,検査受検者における年齢別の比較では,男性は20歳代と30歳代で検査数全体の60~70%,女性では20歳代が50%を占めていた.5年間の陽性数は,男性が370件,女性が4件と男性での陽性例が多く,男性では特に2021年の陽性率が1.16%と最も高かった.一方,行動制限を伴う感染防止対策がとられたCOVID-19の流行下においても東京都新宿東口検査・相談室の検査数は,年間10,000件以上を維持し,東京都における無料匿名HIV検査の中心的な役割を示した.今後のHIV/AIDS撲滅のためには,無料匿名検査機関におけるHIV検査体制の充実や相談事業の継続,推進は重要なキーポイントとなると考えられた. |
|
HIV検査,新型コロナウイルス感染症(COVID-19),無料匿名HIV検査 |
|
東京都感染症発生動向調査事業における呼吸器ウイルス検出状況(2023年度) |
|---|
|
2023年度,東京都健康安全研究センターに感染症発生動向調査の呼吸器感染症関連で搬入された臨床検体(いわゆるインフルエンザ様疾患)を対象に,ウイルス検査および型別検査を実施した.その結果,インフルエンザについては,4月~12月ではAH1pdmとAH3亜型が主であったが,2024年1月以降はB型(Victoria系統)が主となった.新型コロナウイルス(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2: SARS-CoV-2)については,インフルエンザ様疾患の9.3%で検出され,変異株スクリーニング検査により種々の変異株に型別された.また,1検体から複数の病原ウイルスが検出された検体は,524検体中49検体であり(9.4%),その内,インフルエンザウイルスとSARS-CoV-2の同時感染は10検体であった. |
|
インフルエンザウイルス,SARS-CoV-2,感染症発生動向調査事業 |
|
東京都におけるSARS-CoV-2抗体価について (2019年12月~2023年11月) |
|---|
|
2020 年から世界で流行した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は,日本でも感染者が述べ3,300 万人を超え,未曽有の大災害の原因となった.これに対し,今までにないスピードでワクチン開発が進められ,世界各地で積極的に接種が行われた.多くのヒトが新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)への感染とワクチン接種により,体内に抗体を保有し,その増減を調べることは感染者の割合と市民の免疫をおおよそに把握することにつながるため,血清疫学的に利用されてきた.今回,当センターに性感染症検査として搬入された血液を用いて,2019 年12 月から2023 年11 月までの期間においてSARS-CoV-2の抗ヌクレオカプシド蛋白(N)抗体価,抗スパイク蛋白(S)抗体価および中和抗体価を測定した結果,都内のCOVID-19の流行とともに抗N抗体の陽性率の上昇が見られ,ワクチン接種率の上昇と同様に抗S抗体の陽性率は上昇していた.また,抗S抗体価と中和抗体価において,対数のプロットは正の相関を持ち,月ごとの幾何平均値のプロットの概形は非常に似通っていた.定期的に抗体を測定することにより市民のもつ抗体価の全体的な傾向を観察できる可能性が示唆された. |
|
SARS-CoV-2,COVID-19,抗N抗体,抗S抗体,中和抗体 |
|
牛伝染性リンパ腫ウイルスのクローナリティ解析の有用性評価 |
|---|
|
牛伝染性リンパ腫ウイルス(BLV)感染初期の感染細胞はポリクローナルな集団から構成されているが,病態の進行に伴いオリゴクローナル,もしくはモノクローナルな増殖を示し腫瘍を形成する.今回,プロウイルス挿入部位の網羅的増幅法(RAISING法)によるクローナリティ解析を実施し,牛伝染性リンパ腫(EBL)の確定診断及びEBL発症前診断に有効であるかを評価した.確定診断の評価では,過去に病性鑑定を行いEBLと診断した3頭と陰性対照1頭の全血及び腫瘍化組織に対しRASING法を実施し,クローナリティ値(Cv)を求めた.また,各検体は定量PCR法によりBLVプロウイルス量(PVL)を求めた.その結果,EBLと診断した牛全検体のCvは高値となり,陰性対照のCvは低値であった.また,PVLは全検体で高値とはならなかった.さらに,生前診断の評価では,EBLと診断した5頭の生前の全血に対しCv及びPVLを求めた結果,5頭の発症前の検体のCvは高値に至らなかったが,うち1頭は発症3年前の時点でCvが少し上昇した.以上より,RAISING法は確定診断を強力に補強するツールであることが明らかとなった.一方で,生前診断への活用については,一部の牛ではCvが上昇しRAISING法の有用性が示唆されたが,今後もデータを収集し精度を高めていく必要がある. |
|
牛伝染性リンパ腫, クローナリティ解析, RAISING法, プロウイルス量, クローナル増殖 |
論文Ⅱ 医薬品等に関する調査研究
| マオウに含まれるエフェドリン類の一斉分析法の検討 |
|---|
|
当センターでは,薬事監視員が収去・試買等を行った健康食品や危険ドラッグ製品の試験検査を行っている.近年,他県において,植物のマオウを混入させた製品の流通事例が報告されており,マオウの同定法の確立が求められている.そこで,エフェドリン類6成分について,タンデム質量分析計付液体クロマトグラフを用いた一斉分析法及び抽出法を検討した.その結果,エフェドリン類6成分を8分以内に検出し,分離も良好な分析条件を確立した.また,エフェドリン類の迅速な確認に適した前処理法及び均一な抽出効率で抽出するための前処理法を確立した. |
|
健康食品,危険ドラッグ,マオウ,エフェドリン,LC-MS/MS |
論文Ⅲ 食品等に関する調査研究
|
アンモニア水を使用しない食品中のグリチルリチン酸およびステビア甘味料一斉分析法 |
|---|
|
クリーンアナリシスに配慮した効率的かつ回収率の向上を図ることを目的とし,アンモニア水を使用しないグリチルリチン酸(GA,カンゾウ抽出物を含む)およびステビア甘味料(ステビオシド(SS),レバウジオシドA(RS))一斉前処理法ならびにLC-PDAによる同時測定条件について検討した.その結果,トリス緩衝液・メタノール混液を用いた直接抽出および固相抽出による効率的な前処理法とLC-PDAによる良好な同時測定条件を確立した.トリス緩衝液は,トリス塩基とトリス塩酸塩を使用することで,塩酸によるpH調整を不要とした.また,ODSカラムで移動相にギ酸およびアセトニトリルを用いたLC-PDAによるグラジエント測定条件を構築した.これにより,1分析あたり30分以内で両甘味料の良好な同時測定が可能となった.12種類の食品について添加回収試験を行った結果,SS,RSは90%以上,GAは70%以上と良好な回収率であった.また,SS,RSは既存法と同等性が確認された.一方,GAでは食品により厚生労働省通知「食品中の食品添加物分析法」(通知法)の検査法による定量値と比較し差があった.これは,本法と通知法における抽出溶液の組成の違いおよび試料量と抽出溶液量の比率の違いに起因していた.米菓,スナック菓子およびポテトチップスにおいては,抽出溶液に水を多く含む本法の方が,通知法より2.1–16.0倍高い添加回収率が得られ,日常検査に有用だと考えられる. |
| 食品添加物,甘味料,グリチルリチン酸,カンゾウ抽出物,ステビア甘味料,ステビオシド,レバウジオシドA,アンモニア水,トリス緩衝液,LC-PDA |
|
化学物質及び自然毒による食中毒事件例(令和3年~令和5年) |
|---|
|
令和3年から令和5年に東京都内で発生した化学物質や自然毒による食中毒及び有症苦情事例のうち,原因が明らかとなった5事例について報告し,今後の食中毒等予防及び発生時における迅速な検査の参考とする.(事例1)給食でサンマの梅味噌焼きを喫食した43名中17名がアレルギー様症状を呈した.薄層クロマトグラフ(TLC)及び高速液体クロマトグラフ(HPLC)で分析をしたところ,サンマの梅味噌焼きからヒスタミンを検出した.(事例2及び3)ジャガイモを喫食後30分から6時間後に腹痛,嘔吐,頭痛,発熱を呈した2つの事例について液体クロマトグラフ-タンデム質量分析計(LC-MS/MS)による分析を行ったところ,α-ソラニン及びα-チャコニンを検出した.(事例4)コーヒーに洗浄漂白剤が混入した事例であり,定性検査の結果,界面活性剤を検出した.(事例5)ウリ科植物とハマグリの炒め物を喫食した3名中3名が喫食後10分から5時間後に下痢や腹痛等の消化器症状を呈した.LC-MS/MS分析によりウリ科植物からククルビタシンB,ククルビタシンD及びククルビタシンEが検出された.(事例6)公園に生えていたキノコを喫食した4名中4名が錯乱,意識もうろう,嘔吐等の神経症状を呈した.キノコ残品について検査したところテングタケと判明した. |
| 化学性食中毒,ヒスタミン,サンマ,α-ソラニン,α-チャコニン,ジャガイモ,界面活性剤,ククルビタシン類,ウリ科植物,テングタケ |
|
食品の苦情事例(令和4年度~令和5年度) |
|---|
|
令和4年度から令和5年度に検査を実施した食品苦情に関わる11事例のうち4事例を報告し,今後の苦情原因解明の参考とする.(1)弁当に混入していたビニール様片は,官能試験(外観),顕微鏡観察及びフーリエ変換赤外分光分析を行った結果,弁当トレーのバルク包装袋の一部と推定された.(2)焼きそばのシャボン玉液様異味は,発泡試験,陰イオン系界面活性剤試験,非イオン系界面活性剤試験及び界面活性剤薄層クロマトグラフィー試験を行った結果,当該店で使用していた洗剤の混入が原因と推定された.(3)いなり寿司から出てきた歯の詰め物様物は,官能試験(外観),顕微鏡観察及び蛍光X線分析を行った結果,金合金を主成分とする歯の詰め物と推定された.(4)和生菓子に混入していた毛髪様物は,官能試験(外観),顕微鏡観察及び種の鑑別試験を行った結果,イヌの毛と推定された. |
|
食品苦情,異物,異味,ビニール,洗剤,歯の詰め物,金合金,イヌ,毛 |
|
食品中の二酸化硫黄及び亜硫酸塩類の含有量実態調査 |
|---|
|
二酸化硫黄及び亜硫酸塩類(SO2)は,食品添加物として漂白剤,保存料,酸化防止剤の目的で使われている.一方,検査時に,食品成分中の含硫化合物由来と考えられるSO2が検出されることも多く,食品添加物として添加されたものとの判別は,食品表示法への適合を判定する上で重要である.そこで,生鮮食品やSO2の添加表示がない加工食品について,性能評価済みの液体クロマトグラフィーによる分析法を用い,SO2含有量の実態調査を行った.生鮮食品では,赤えび,たまねぎ,にんにく,フラワーえび,アーリーレッド,下仁田ねぎで今回設定した定量限界値1.0 µg/g以上のSO2を検出した.添加表示がない加工食品では,含硫化合物を含む食品を原材料とするにんにく加工品,切り干し大根,干ししいたけ等のほかに,ワイン,ビール,ぶどうジュース,ゼラチン,しょう油等からも検出した.ワインやビール中のSO2は製造工程で使用される酵母由来であると考えられたが,ワインでは含有量が10 µg/gを超えるものもあった. |
| 実態調査,二酸化硫黄,亜硫酸塩類,食品,HPLC |
|
清涼飲料水及びビール中のパラオキシ安息香酸ヘプチルの分析法の検討 |
|---|
|
アメリカで清涼飲料水及びビールに使用が許可されている指定外添加物のパラオキシ安息香酸ヘプチルについて,抽出・精製の検討とHPLCによる定量法,LC-MS/MSによる確認法を検討した.透析液を80%メタノールとして,透析によるパラオキシ安息香酸ヘプチルの抽出・精製を行ったところ80%以上の回収率を得た.HPLCによる定量法ついては,日常検査を行う9種保存料と同時分析できるようにパラオキシ安息香酸ヘプチルの分析条件を検討し,良好な結果が得られた.パラオキシ安息香酸ヘプチルは0.05~1.25 µg/mLの範囲で直線性を示し,検出限界は0.05 µg/mLであった.LC-MS/MSによる定性確認はMRMモードを用い,2種のプロダクトイオンによる観察を行い,確認方法として有用であることを明らかにした. |
| 食品添加物,保存料,パラオキシ安息香酸ヘプチル,透析法,HPLC,LC-MS/MS |
|
コチニール色素を使用した輸入マシュマロの4-アミノカルミン酸検出事例 |
|---|
|
2022年に収去されたコチニール色素の表示がある米国産マシュマロ(ピンク色)から,コチニール色素とは異なる赤紫色の不明色素をTLC上で検出した.過去の事例から,不明色素は4-アミノカルミン酸(耐酸性コチニール)であると考え,通知法に準じてHPLC及びLC-MSにより分析を行い,検査体制を整備して当該色素が4-アミノカルミン酸であることを確認した.当センターにおいて同色素の検出事例は初であった.近年,国内外で4-アミノカルミン酸の検出事例が報告されていることから,今後も最新情報や事例についての情報を蓄積し,日常検査に活かしていくことが必要であると考えられた.また,4-アミノカルミン酸を高選択・高感度に分析するため,LC-MS/MS条件の検討と最適化もあわせて実施し,新規項目に対応できる体制の強化を図った. |
|
4-アミノカルミン酸,耐酸性コチニール,コチニール色素,カルミン酸,着色料,TLC,HPLC,LC-MS/MS,食品添加物 |
|
液体クロマトグラフ‐タンデム型質量分析計による 玄米中残留農薬一斉分析法の妥当性評価 |
|---|
|
昨年,農薬283成分を対象に開発した玄米中残留農薬一斉分析法の対象農薬を拡充し,対象外としていた126成分について,異なる機種の液体クロマトグラフ‐タンデム型質量分析計を用いて玄米中残留農薬一斉分析法の妥当性評価を行った.2濃度(0.01および0.1 µg/g),2併行,5日間の添加回収試験を実施し,妥当性評価ガイドラインの適否判断を行ったところ,126成分中124成分(98.4%)が目標値に適合した.昨年開発した一斉分析法では250成分が妥当性評価ガイドラインの目標値に適合しており,本実験と重複している68成分を考慮すると,妥当性評価ガイドラインの目標値に適合した農薬数は計306成分(250 + 124 – 68 = 306)となった.本実験により,計306成分の農薬について開発法における試料前処理法の有用性が示され,行政検査への活用が可能になった. |
|
残留農薬,玄米,液体クロマトグラフ‐タンデム型質量分析計,LC-MS/MS,妥当性評価 |
|
魚介類中の残留有機塩素系農薬実態調査(令和3~4年度) |
|---|
|
東京都は,都民の食の安全・安心を守るため,魚介類中における有機塩素系農薬の残留実態を継続的に把握している.令和3年4月から令和5年3月において都内に流通していた魚介類を対象とし,昨今の喫食事情を反映させた多種多様な63種80食品について調査を実施した.21種24食品(検出率30%)から4種類の有機塩素系農薬(DDT,クロルデン,ノナクロル及びヘキサクロロベンゼン)を0.001–0.023 ppmの範囲で検出した.この調査結果より,残留量と魚介類中脂肪量との相関,魚の生活サイクルと残留の関係について考察した.調査検体において,食品衛生法の残留基準値(MRL)を超えたものは認められなかった.今後飼育環境の変化が考えられる鮭や消費者の喫食が増加すると考えられるアカムツから有機塩素系農薬を検出したことから,今後も継続的に調査を行い,残留実態を把握していく必要があることを示唆した. |
|
残留農薬,魚介類,有機塩素系農薬,残留基準値 |
|
畜水産物中の残留有機塩素系農薬実態調査(令和5年度) |
|---|
|
東京都では有機塩素系農薬による健康危害未然防止のために,東京都内に流通している畜水産物中の残留の実態調査を継続して行っている.令和5年4月から令和6年3月の間に,食肉,生乳,鶏卵,魚介類及びその加工品等,畜水産物12種124食品について食品毎に設定された残留基準値(MRL)を超えていないか調査を実施した.その結果を報告するとともに,既報と比較して残留の変遷について考察した. 食肉,鶏卵では有機塩素系農薬を検出しなかった.一方,生乳4食品,サワラ1食品の合計5食品(検出率4%)から1種類の有機塩素系農薬(DDT)を食品衛生法の残留農薬基準値を超えない0.0001-0.0002 ppmの範囲で検出した. DDTとその代謝体についてはこれまでにも検出例を報告している.このことから,有機塩素系農薬の使用が禁止され長期間たっても,乳牛の飼育環境中に低濃度の残留が続いていること,また生物濃縮等により海産物中に農薬の残留がみられることが示唆された. |
|
残留農薬,畜水産物,有機塩素系農薬,残留基準値 |
論文Ⅳ 生活環境に関する調査研究
|
東京都新宿区における49×49レスポンスマトリックス法による空間線量率の推移 |
|---|
|
東京都健康安全研究センターに設置したモニタリングポストにより測定した2007年1月1日から2023年12月31日までの空間線量率を,49×49のレスポンスマトリックス法を用いて解析した.人工線量率は,福島第一原子力発電所事故以前は0 nGy/hであったが,事故後約90 nGy/hまで上昇し,その後徐々に減少した.2017年3月の地上への更新・移設に伴い,人工線量率は低下して0 nGy/hになった.これは外構整備に伴い周辺の土壌を入れ替えたことで,事故由来の放射性セシウムがほぼ検出されなくなったためと推察される.環境γ線線量率は,今後も地上移設後のレベルが継続すると考えられる.2011年3月12日から5月15日におけるエネルギー帯ごとの核種を推定し,線量率強度の時間的推移を考察した.降水がない3月15日から16日は,プルームの通過による一過性の線量率上昇が4回あり,1回目と2回目はヨウ素132の寄与が最も高く,3回目と4回目は大半がキセノン133であり,1回目及び2回目とは異なる組成のプルームであったことが示唆された.3月21日から23日は降水によって放射性物質が湿性沈着したため,線量率が高い状態が継続した後徐々に減衰していった.テルル132は3月中,ヨウ素131は4月中旬過ぎに消失し,以降はセシウム134及びセシウム137が残存した. |
|
モニタリングポスト,空間線量率,波高分布,レスポンスマトリックス法,福島第一原子力発電所事故,放射性プルーム,ウラン系列,トリウム系列,カリウム40,ヨウ素131,ヨウ素132,キセノン133,セシウム134,セシウム137 |
|
東京都健康安全研究センター排水の測定結果について |
|---|
|
東京23区内の事業所排水に対しては,下水排除基準(東京23区内)が設定され,公共下水道へ放出される排水中の有害物質について基準値が設けられている.東京都健康安全研究センターも下水排除基準で定められる施設に該当し,各規制項目の基準値に適合していることを確認する必要がある.令和5年度の当センターの排水測定では,金属類元素,沃素消費量,浮遊性物質,燐及びノルマルヘキサン抽出物質で検出が見られたが,金属類元素の検出頻度が最も高かった.金属類元素の検査精度確保のために妥当性評価を行ったところ,良好な結果が得られた.令和5年度にはほう素,亜鉛及び鉄(溶解性)が複数回検出されたが,基準値を超過することはなく,その他の金属類元素については全ての測定月で定量下限値未満であった.今後も検査精度を保った検査を継続していくことが必要である. |
|
排水,金属類,誘導結合プラズマ-質量分析(ICP-MS),一斉分析 |
|
東京都(多摩地域及び島しょ地域)におけるプール水及びジャグジー水等からの レジオネラ属菌の検出状況(令和3年度~令和5年度) |
|---|
|
東京都におけるレジオネラ症防止対策の一環として,令和3年度~令和5年度に多摩地区及び島しょ地域に所在する施設のプール水及びジャグジー水等740件についてレジオネラ属菌を調査した.レジオネラの水質基準である「検出されないこと」(10 CFU/100mL未満)を超過した割合は,6.4%であった.その内訳は,プール水で2.7%,ジャグジー水等では13.6%であった.また,レジオネラ属菌が検出された147検体について抗血清,Multiplex-PCR法,リアルタイムPCR法を用いて209株の菌種を同定した.その結果, Legionella pneumophilaが198株で94.7%を占めた.また,L. spp.分離株についてシーケンシング法を行った結果,L. maceachernii,L. nautarum,L. sainthelensiが同定された. |
| レジオネラ属菌,レジオネラ症,プール水,ジャグジー水,遊離残留塩素,血清群,迅速検査法 |