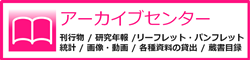*記載内容
| タイトル |
|---|
| 和文要旨 |
| キーワード |
総説
|
微生物分野の健康危機発生時における東京都健康安全研究センターとしての役割 |
|---|
|
東京都における過去の微生物分野の健康危機には,重症急性呼吸器呼吸器症候群(SARS),新型インフルエンザ(インフルエンザAH1N1pdm09),中東呼吸器症候群(MERS),デング熱およびA型肝炎等が挙げられ,2020年からは新型コロナウイルス(COVID-19)対応が始まった.東京都健康安全研究センター(健安研)は東京都の地方衛生研究所(地衛研)としてそれぞれの健康危機管理で,検査を中心に対応を行ってきた.特に,COVID-19では1日当たりの核酸増幅検査総数が問われ,その後,変異株スクリーニング検査や次世代シーケンサーによる変異株のモニタリングを実施し,ホームページ上でも専門的な病原体情報を公開する役割を担った.今後も様々な健康危機管理の発生が予測されるが,COVID-19での対応がデフォルトとなり,2023年に地衛研が法制化されたことで,地衛研に求められる役割はますます大きくなる.時代は変遷し,職員も入れ替わっていかざるを得ないが,今までの健康危機の経験をレガシーとし,試行錯誤や失敗を恐れずに今後の健康危機に立ち向かわなければならない.本稿ではCOVID-19等の対策の中で,健安研が経験した様々な対応を列挙し,改めて健康危機発生時に果たした健安研の役割を考えてみることとする. |
|
健康危機管理,新型コロナウイルス(SARS-CoV-2),新型コロナウイルス感染症(COVID-19),地方衛生研究所 |
| 東京都における食品中食品添加物の検査 |
|---|
|
食生活は健康な身体を維持するために欠くことのできない営みであると同時に,社会的・文化的な営みでもある.近年,食のグローバル化により多種多様な食品が流通するようになった.また,インターネット等を介して,食に関する様々な情報に触れる機会が増えている.さらに,コロナ禍においては,自炊する人や宅配を利用する人が増加するなど,食を取り巻く環境,人々の意識や行動は変化し続けている.このような変化の中においても,食の安全安心への関心は極めて高い.本稿では,最近の食品添加物に関する話題と東京都で実施している食品添加物の一日摂取量調査,食品中食品添加物の分析法開発,天然由来の食品添加物含有量調査の概要について紹介する.また,東京都では,都内で流通している食品について,食品衛生法及び食品表示法に基づいた食品添加物の収去検査を実施している.平成18年度~令和2年度の15年間に当センター食品化学部食品添加物研究科で実施した検査結果の概要と事例についても紹介する. |
|
食品添加物,食の安全安心,検査,食品衛生法,食品表示法 |
論文Ⅰ 感染症等に関する調査研究
|
都内流通食肉における基質特異性拡張型βラクタマーゼ(ESBL)およびAmpC型βラクタマーゼ産生大腸菌の検出状況 |
|---|
|
食肉における基質特異性拡張型βラクタマーゼ(ESBL)およびAmpC型βラクタマーゼ(AmpC)産生大腸菌の検出状況を把握するために,2011年から2019年に東京都で流通した鶏肉,牛肉および豚肉を対象として調査を行った.食肉から分離された大腸菌1,604株のうち,ESBL産生株は,国産鶏肉由来22/714株(3.1%),輸入鶏肉由来48/324株(14.8%)および国産牛肉由来1/127株(0.8%)で,AmpC産生株は,国産鶏肉由来14/714株(2.0%),輸入鶏肉由来22/324株(6.8%),国産牛肉由来2/127株(1.6%)および国産豚肉由来1/169株(0.6%)であった.ESBL産生株の遺伝子型は,国産鶏肉由来株ではCTX-M-1 group(27.3%)とCTX-M-2 group(27.3%)が,輸入鶏肉由来株ではCTX-M-2 group(50.0%)とCTX-M-8 group(29.2%)が多く検出され,国産牛肉由来ESBL産生株の遺伝子型はCTX-M-9 groupであった.また,AmpC産生株の遺伝子型はすべてCITであった.食品から分離されるESBL/AmpC産生大腸菌の動向を把握するために,今後も継続してモニタリングや解析等の調査を行っていく必要がある. |
|
食肉,薬剤耐性,ESBL産生大腸菌,AmpC産生大腸菌 |
| 東京都において分離されたSevere acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) オミクロン株の分離培養に用いる培養細胞の検討 |
|---|
|
SARS-CoV-2オミクロン株は,当初の武漢株からデルタ株などに比べスパイク蛋白に多くの変異を持っており,デルタ株までの分離培養において最も分離成績が良好であったVero E6/TMPRSS2細胞を用いても分離が困難になってきた.そこで,オミクロン株の分離率の向上を目的に,維持培地にアムホテリシンBを添加したVero E6細胞では,添加前の分離率が35.7%(91/255検体)から45.9%(111/242検体)まで向上した.しかしながら,更なる変異株の出現により分離できない変異株も散見されるようになってきたことから,Vero E6/TMPRSS2/T2A/ACE2細胞を用いた分離培養を試みたところ,Vero E6/TMPRSS2細胞で35.7%(91/255検体)の分離率が,Vero E6/TMPRSS2/ T2A/ACE2細胞では52.6%(120/228検体)まで向上した.このことから,オミクロン株を分離するために用いる細胞としてVero E6/TMPRSS2/T2A/ACE2細胞が現段階では最も適していると考えられた. |
|
SARS-CoV-2,デルタ株,オミクロン株,Vero E6細胞,Vero E6/TMPRSS2/T2A/ACE2細胞 |
|
新型コロナウイルス感染症流行時の都内における食中毒発生状況(2020年~2022年) |
|---|
|
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的大流行により,国内で複数回の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(まん延防止等重点措置を含む)が発令され,行動制限を伴う感染防止対策が取られた.都内飲食店においても休業要請・営業時間の短縮,人数制限,酒類の提供禁止などの対策が取られた.その結果,例年と比べ都内の食中毒の事件数は減少し,患者数は記録がある1949年以降で最少となった.病因物質別では細菌,ウイルスによる食中毒は減少したが,寄生虫による食中毒には大きな変化は認められなかった.また,COVID-19流行後に新しく弁当製造を開始した施設による食中毒事例やCOVID-19感染対策業務に対応するため,前日調理を行ったことで発生した食中毒事例も散見された. |
| 食中毒,新型コロナウイルス感染症(COVID-19),ウエルシュ菌,腸管出血性大腸菌O157,前日調理 |
|
都内小児科定点医療機関において検出されたA群溶血性レンサ球菌の血清型別および薬剤感受性状況(2015年~2022年) |
|---|
|
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は,感染症法において五類の小児科定点把握疾患である.東京都健康安全研究センターでは患者から分離されたStreptococcus pyogenesについて,T血清型別等の調査を実施している.今回,2015年~2022年に感染症発生動向調査として病原体定点で採取された咽頭ぬぐい液より分離された560 株についてT血清型別を行い,そのうちの558株について薬剤感受性試験を実施した.分離された菌株数を年次別にみると,例年に比べ2020年は半減し,さらに2021年及び2022年は例年の10%以下に激減していた.理由としては,新型コロナウイルス感染症の影響によりA群溶血性レンサ球菌咽頭炎患者が激減したことに伴って,当センターへの搬入検体が減少したためと考えられた.T血清型別では,13種類のT血清型に分類され,多い順に1型,12型,4型,B3264型,28型等であった.薬剤感受性試験は,9薬剤について微量液体希釈法にて実施した結果,βラクタム系薬剤に対する耐性は見られず,テトラサイクリン耐性は8.5%,クロラムフェニコール耐性は1株であった.マクロライド系薬剤であるエリスロマイシンおよびクラリスロマイシンに対する耐性は共に27.2%であり,クリンダマイシンに対する耐性は8.1%であった.T血清型別結果について,劇症型溶血性レンサ球菌感染症由来株と比較してみると,咽頭炎で多く見られる型(1型やB3264型)とほとんど見られない型(4型や12型)があることが分かった.今後も,調査を継続し動向を注視する必要がある. |
| A群溶血性レンサ球菌,咽頭炎,T血清型,薬剤感受性 |
| 東京都における梅毒無料匿名検査の陽性率の推移(2015年度~2022年度) |
|---|
|
東京都では性感染症対策事業として,特別区保健所ならびに東京都新宿東口検査・相談室(旧名称:東京都南新宿検査・相談室)において梅毒の無料匿名検査を行っている.本事業では,保健所等で受検者から採取した血液を東京都健康安全研究センターへと搬入し,梅毒トレポネーマ抗体ならびに非トレポネーマ脂質抗体をそれぞれ検出することにより梅毒感染を検査する.今回,2015年度から2022年度において当センターで実施したトレポネーマ抗原を検出するTreponema Pallidum Latex-Agglutination(TPLA)法と非トレポネーマ脂質抗体を検出するRapid Plasma Reagin(RPR)法による検査結果を集計し,施設,検査時期に関する分析を行った. |
|
梅毒,無料匿名検査,抗体検査,検査陽性率,TPLA法,RPR法 |
| 東京都におけるつつが虫病リケッチアの検出状況(2020年度から2022年度) |
|---|
|
2020年4月から2022年3月までに東京都内の保健所(主に伊豆諸島)で採取されたツツガムシ病患者21検体について、Orientia tsutsugamushi特異的56KDaポリペプチドコード領域のnested-PCR検査を行った。PCR陽性のものは塩基配列を決定し、系統樹解析を行った。その結果,21検体中16検体からO. tsutsugamushi遺伝子が検出され,伊豆諸島のO. tsutsugamushiは3つの血清型に分類された.各島におけるO.tsutsugamushiの血清型分類の結果,伊豆大島ではKarp株とKawasaki株,三宅島,御蔵島,式根島ではKuroki株,新島ではKawasaki株が検出され,島しょ部でのつつが虫病は3つの異なる血清型によって引き起こされていることが示された. |
|
つつが虫病リケッチア,ツツガムシ,Orientia tsutsugamushi,tick-borne disease,rickettsiosis |
| 都内下水中の新型コロナウイルスモニタリング調査(2021年度~2022年度) |
|---|
|
東京都では,2020年1月に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者が確認されて以降,2023年5月現在,累計 400万人以上の感染者が報告されている.新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)は,感染者の唾液や喀痰,糞便等から排出されるため,これらが集積される下水処理施設の流入下水を対象とした,SARS-CoV-2モニタリングが注目され,各国で実施されている.今回,2021年5月から2023年3月までに都内水再生センター20カ所(区部13カ所,多摩地域7カ所)で採取された流入下水を対象に,全自動遺伝子検査装置を用いた高感度な検出法によるSARS-CoV-2モニタリングを実施した.その結果,区部においては第6波以前では下水試料203件中86件,第6波以降では741件中738件,多摩地域においては第7波以降の142件中137件が陽性となった.さらに,前処理した下水試料を10倍段階希釈し検査することで,都内における流行状況を多面的に把握できる可能性が示唆された. |
|
下水,新型コロナウイルス,SARS-CoV-2,沈渣,全自動遺伝子検査装置 |
|
東京都内で検出されたデングウイルスの遺伝子解析結果(2015年度~2022年度) |
|---|
|
東京都では,2014年のデングウイルス(DENV)国内感染例の発生以後,詳細な遺伝子解析検査の体制を整え,デングウイルス遺伝子解析の結果を集積している.2015年4月から2023年3月までに,東京都の積極的疫学調査事業等でデング熱疑いまたはデング熱確定例として搬入された患者検体について,検出状況および遺伝子解析結果をまとめた.476検体中220検体からデングウイルスを検出し,夏季に増加する傾向が見られた.また,血清型の内訳はDENV-2型,1型,3型,4型の順に多く,血清型別に分子系統樹解析を行ったところ,感染地域別に特徴的なクラスターが形成され,輸入症例の感染地域の推定にも一定の有用性があることが示唆された.今後もデータの蓄積を継続することで,国内感染発生の際には早期に探知することや,関連患者の調査やDENV感染蚊の駆除に活用し,迅速に流行を収束させることに貢献できるものと考えられる. |
|
デング熱,デングウイルス,血清型別,遺伝子型別,分子系統樹解析 |
|
東京都内で分離された新型コロナウイルス(オミクロン株)の次世代シーケンサーを用いた遺伝子解析(2022年9月~2023年3月) |
|---|
|
2019年12月に発生した新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の亜系統オミクロン株による新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は世界中で発生が続いている.国内第7波(2022年7月~9月)および第8波(2022年11月~2023年1月)における東京都内でCOVID-19患者から分離された株を次世代シーケンサーで解析した.その結果,都内COVID-19患者から第7波ではオミクロン株亜系統のBA.5が,第8波はBA.2とBA.5の各派生系統およびリコンビナント株のXBB系統が分離された.系統樹解析および変異解析より,オミクロン株は感染力とともに免疫逃避能が向上するアミノ酸変異の蓄積を重ねていた.また,オミクロン株に持続感染していた長期入院患者から分離された株について解析した結果,同時期の分離株と比較してプロテアーゼ合成領域を含む全長に多くの変異を有していた. |
|
SARS-CoV-2,COVID-19,分離培養株,オミクロン株,次世代シーケンサー,系統樹解析 |
|
東京都における新型コロナウイルスの全ゲノム解析(2022年6月~2023年5月) |
|---|
|
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は2019年12月に中国で初めて確認され,これまでに数多くの新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)変異株が世界中で報告された.2022年1月から始まった第6波以降は,オミクロン株派生系統のBA.1からBA.5,XBBまでの系統であり,各系統はさらに多くの亜系統に細分化している.東京都では変異株サーベイランスを目的に,SARS-CoV-2の全ゲノム解析を実施してきた.今回,2022年6月1日から2023年5月31日の間にNGS解析を実施した113,505件を解析した結果,2022年6月まではBA.2系統が主流であり,2022年7月から2023年2月まではBA.5系統のBA.5.2.1系統,2023年3月以降はXBB系統のXBB.1.5系統が主流となっていた.都内で検出されたXBB系統の系統樹解析では,XBB.1.5系統,XBB.1.9系統,XBB.1.16系統のクレードと,XBB.2.3系統のクレードに大きく分かれ,それぞれ海外株を含むクラスターを形成した.これらの結果より,全ゲノム解析から亜系統の分類を集計することがCOVID-19の流行状況の詳細な把握に有用と考えられた. |
| COVID-19,SARS-CoV-2,次世代シーケンサー(NGS),亜系統,系統樹解析 |
|
新型コロナウイルス感染症の持続感染事例におけるSARS-CoV-2遺伝子解析 |
|---|
|
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)が2019年末に中国で初めて検出された後,アルファ株,デルタ株やオミクロン株などの変異株が出現するごとに流行の波が起こり,現在も完全なる収束には至っていない.特にオミクロン株から派生した亜系統は,免疫逃避能が高いアミノ酸変異を多数獲得しながら急速かつ同時に出現し,感染者数の増加やワクチンの開発などに影響を与えてきた.また,免疫不全患者の体内での持続感染は新たな変異株の発生につながりやすいことが報告されている.本報告では,都内において長期にわたってSARS-CoV-2に感染した2症例について,臨床検体中のSARS-CoV-2を次世代シーケンサー(NGS)による全ゲノムの比較解析を行い,持続感染によって生じた変異について調査した.その結果,SARS-CoV-2の遺伝子変異は通常1か月に1~2塩基程度起こるとされているが,持続感染者の体内ではそれよりも速いスピードで変異が生じていた.また,持続感染により生じたアミノ酸変異には,オミクロン株の亜系統に見られる特徴的な変異が含まれていた.このことから,免疫機能の低下した人の体内でSARS-CoV-2の持続感染が起こると,通常よりも速いスピードで免疫逃避能の高いアミノ酸変異を獲得しやすいことが示唆された. |
|
SARS-CoV-2,COVID-19,持続感染,次世代シーケンサー,変異 |
|
新型コロナウイルスワクチン接種者及びHIV臨床検体,E型肝炎臨床検体における血中サイトカイン量の測定 |
|---|
|
病原体が体内に侵入すると貪食細胞に取り込まれ,種々のサイトカインが分泌される.それらが協調的に働くことで免疫系が調整されて生体防御が行われる.新型コロナウイルス感染症ではInterleukin-15(IL-15),Interleukin-6(IL-6),Interferon-gamma(IFN-γ)などの血中サイトカイン上昇が報告されている.本研究ではワクチン接種やウイルス感染による血中サイトカイン量変化の観察を目的とし,新型コロナウイルスワクチンを接種した当センター職員から得た血清並びにHIV検査受検者,E型肝炎患者の血清を用いてIL-15,IL-6,IFN-γ及びIFN-γ誘導性ケモカインInterferon-gamma-induced protein 10(IP-10)の測定を,酵素免疫測定法 Enzyme-Linked Immunosorbent Assay(ELISA)法で行った.その結果,新型コロナウイルスワクチン接種者の血清ではIL-6については量的変化が見られず,IL-15については3回目接種10日後の検体で濃度の上昇が見られ,IFN-γ及びIP-10の濃度については2回目接種3日後の検体での上昇が見られた.また,HIV陽性検体ではIP-10について濃度の上昇が見られ,E型肝炎患者検体では,IP-10,IL-6について濃度の上昇が見られた. |
|
サイトカイン,ELISA法,新型コロナウイルス(SARS-CoV-2),新型コロナウイルスワクチン接種,副反応,HIV,E型肝炎 |
|
新型コロナウイルス陽性検体における核酸多項目同時検出試薬を用いた網羅的な検索 |
|---|
|
2023年5月,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が5類感染症に移行し,感染症防止対策が個人・事業者の自主的な判断と取組が尊重されるようになった.社会経済活動,生活様式が活発となったことで,コロナ流行以前に近い日常を送れるようになり,流行が抑制されていた呼吸器系感染症等に再度,流行の兆しがみられるようになった.今回,2023年1月30日から2023年3月31日の期間に,東京都健康安全研究センターに搬入された民間検査機関により新型コロナウイルス検査陽性となった患者検体(咽頭拭い液または唾液)について,新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスの同時感染,またその他病原体による重複感染の探知を目的として,核酸多項目同時検出試薬を用いて病原体の検索を行った.その結果,対象とした120検体中4検体(3.3%)からインフルエンザウイルスが検出され,ヒトコロナウイルスとの重複検出は8検体(6.6%)であり,様々な呼吸器系病原体の網羅的な検出にFilmArray呼吸器パネル2.1の使用は適していると思われた.感染症発生動向調査の観点では,COVID-19の中にインフルエンザウイルス感染者やその他のウイルス感染者が含まれている可能性は少ないことから,SARS-CoV-2の検体を集める場合にはCOVID-19患者検体を集め,インフルエンザウイルスの検体を集める場合には,インフルエンザ患者検体を集めるべきであることが結論づけられた. |
|
新型コロナウイルス感染症,SARS-CoV-2,インフルエンザウイルス,重複感染 |
|
都内動物取扱業(販売業及び展示業)における取扱動物の動物由来感染症起因病原体保有実態調査(令和2年度~令和4年度) |
|---|
|
東京都では,都民の飼養する動物や不特定多数の都民がふれあう動物に由来する感染症について,その発生を未然に防止するため,都の動物由来感染症予防体制整備事業実施要綱に基づいた調査を実施している.今回,令和2年度から令和4年度までに都内ペットショップで販売されていた犬133頭及び猫101頭と,都内動物園等でふれあい展示されていた動物26頭を対象に,各種の病原体保有状況を調査した.調査の結果,ペットショップで販売されていた動物から,サルモネラ属菌(犬1検体),病原大腸菌(犬22検体,猫2検体),犬小回虫卵(犬1検体),ジアルジア(犬32検体,猫9検体),糞線虫(犬2検体),皮膚糸状菌(犬12検体,猫14検体)が検出された.また,動物園等でふれあい展示されていた動物からは,病原大腸菌(山羊1頭,羊6頭)が検出された.このように,動物取扱業の取扱動物は動物由来感染症の病原体を保有している場合がある.施設管理者へは施設内で交差感染により感染が広がる可能性があることを啓発し,適正な衛生管理を引き続き指導するとともに,動物由来感染症について都民に対し普及啓発することが重要と考えられた. |
|
動物由来感染症,動物取扱業,ペットショップ,ふれあい動物園,サルモネラ属菌,病原大腸菌,犬小回虫,ジアルジア,糞線虫,皮膚糸状菌 |
論文Ⅱ 医薬品等に関する調査研究
| 化粧品における配合成分の検査結果(令和4年度) |
|---|
|
令和4年度に搬入された化粧品77製品について,ホルマリン,防腐剤,紫外線吸収剤,タール色素及び承認化粧品成分の製品への表示状況及び検査結果をまとめた.配合禁止成分であるホルマリンは,ホルムアルデヒドとして検査し,検出した製品は1製品であった.防腐剤については,パラオキシ安息香酸エステル類やフェノキシエタノールの検出頻度が高かった.また,表示されていない防腐剤を検出した製品は4製品であった.紫外線吸収剤については,パラメトキシケイ皮酸2-エチルヘキシルや2-[4-(ジエチルアミノ)-2-ヒドロキシベンゾイル]安息香酸ヘキシルエステルの検出頻度が高かった.最大配合量を超過した濃度の紫外線吸収剤を検出した製品はなかった.また,表示されていない紫外線吸収剤を検出した製品もなかった.タール色素については,黄色4号の検出頻度が高かった.承認化粧品成分については,グリチルリチン酸ジカリウムの検出頻度が高かった.最大配合量を超過した濃度の承認化粧品成分を検出した製品はなかった. |
|
化粧品,ホルマリン,ホルムアルデヒド,防腐剤,紫外線吸収剤,タール色素,承認化粧品成分 |
|
色付きのマスクに含まれるホルムアルデヒド及び特定芳香族アミンに関する調査 |
|---|
|
東京都では,健康被害未然防止の観点から先行調査として,「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」(以下,家庭用品規制法と略す)の規制対象外の製品について試買試験を実施している.令和3年度の先行調査では,COVID-19の感染拡大で数多くのマスクが流通している背景があることから,製品の安全性に関する実態を把握する目的で,色付きのマスクに含まれるホルムアルデヒド及び特定芳香族アミンを調査した.家庭用品規制法に準じ,東京都内に流通している色付きのマスク22製品について試験検査を実施したところ,家庭用品規制法の基準である75 µg/gを超えるホルムアルデヒド及び30 µg/gを超える特定芳香族アミンを含有する製品はなかった. |
| マスク,家庭用品,ホルムアルデヒド,アゾ染料,特定芳香族アミン |
論文Ⅲ 食品等に関する調査研究
|
水溶性食物繊維のHPLC-RI分析における代替内部標準物質の検討 |
|---|
|
食物繊維の分析法で用いられる酵素が通知法上変更され,水溶性食物繊維のHPLC-RI分析において従前から内部標準物質として用いていたグリセリンでは正確な測定値が得られない懸念が生じた.そこでグリセリンに替わる内部標準物質として各糖類,糖アルコール類,低級アルコール計19種を検討した.その結果,目的物質及び夾雑物質と分離ができるジエチレングリコールおよびエチレングリコールのうち,さらに分離度の高いジエチレングリコールを内部標準物質として選択した.難消化性デキストリンの測定を行い,旧酵素でグリセリンを内部標準物質としたときの規格基準法との測定結果の同等性を確認した.次に,清涼飲料水中における妥当性を確認した.その結果,1 g/100 mL(食物繊維として0.876 g/100mL)となるように調製した時の真度92.0–96.2%,併行精度7.0–7.1%,および室内精度7.0–7.1%とガイドラインの目標値を満たしていた.水溶性食物繊維の測定においては,内部標準物質にジエチレングリコールを使用することが適切であることを示唆した. |
| 食物繊維,水溶性食物繊維,内部標準物質,ジエチレングリコール,難消化性デキストリン,HPLC-RI |
|
液体クロマトグラフ-誘導結合プラズマ質量分析装置を用いたミネラルウォーター類中の六価クロム分析法の性能評価 |
|---|
|
六価クロム(以下,Cr(VI)とする)は毒性を有する金属元素であり,食品衛生法においてミネラルウォーター類に対し基準値(0.02 mg/L)が規定されている.本研究では液体クロマトグラフ-誘導結合プラズマ質量分析装置(以下,LC-ICP-MSとする)を用いた分析法について検討し,その性能を評価して日常検査への適用の可否を検討した.都内で流通しているミネラルウォーター3種類にそれぞれCr(VI)を添加し,食品中の有害物質等に関する分析法の妥当性ガイドラインに則り性能評価を行った結果,選択性があり,真度100~108%,併行精度2.8%以下,室内精度5.3%以下でいずれも目標値を達成した.以上より,本法は日常検査において有用な方法であると示唆された. |
| クロム,六価クロム,Cr(VI),ミネラルウォーター,液体クロマトグラフ-誘導結合プラズマ質量分析装置,LC-ICP-MS |
|
遺伝子組換え食品の検査結果(令和3年度~令和4年度) |
|---|
|
令和3年4月から令和5年3月までに,東京都で実施した遺伝子組換え食品検査の結果について報告する.国内で流通が認められていない,安全性未審査の遺伝子組換えトウモロコシ(CBH351, Bt10),コメ(63Bt, NNBt, CpTI)およびパパイヤ(PRSV-YK, PRSV-SC, PRSV-HN)を対象とした定性試験を計103検体に対して行った結果,これらの遺伝子組換え作物は検出されなかった.安全性審査済み遺伝子組換え食品について,ダイズ加工食品およびトウモロコシ加工食品166検体の定性試験を行った結果,33検体から組換え遺伝子を検出した.ダイズ穀粒およびトウモロコシ穀粒について,16検体の定量試験を行った結果,意図しない混入率の基準(5%)を超えるものはなかった. |
|
遺伝子組換え食品,PCR,リアルタイムPCR,トウモロコシ,コメ,パパイヤ,ダイズ,加工食品 |
|
加工食品中の特定原材料(卵,乳,小麦,そば)の検査結果(令和3年度~令和4年度) |
|---|
|
食物アレルギーによる健康危害未然防止のために,食品へのアレルギー物質表示が義務化されている.東京都で令和3年4月から令和5年3月に実施した特定原材料検査の結果から,表示が適正に行われているか,その動向を示した.東京都内で製造または流通していた加工食品について,69検体にELISA法によるスクリーニング検査を実施した.乳において23件中1検体,小麦において18件中2検体で陽性を示した.乳陽性の検体はウエスタンブロット法,小麦陽性の検体はPCR法を用いて,おのおの確認検査を行った.その結果,どら焼き1検体を乳陽性と確定した.この原材料表示には、「乳」の記載はなかった.誤食を防ぐために適切な食品表示がなされているか確認するには,今回のような原材料の原料にも着目した加工食品に対する特定原材料の検査の継続的な実施が重要であることを示唆した.また,スクリーニング検査と確認検査の結果の不一致は,粉末原料の麦芽が小麦のELISA法において偽陽性を示したためであった.このことから,原理の異なる確認検査を行う必要性を改めて示すことができた. |
| 食物アレルギー,特定原材料,卵,乳,小麦,そば,ELISA法,ウエスタンブロット法,PCR法 |
|
誘導結合プラズマ質量分析装置を用いた玄米中カドミウム分析法の妥当性評価 |
|---|
|
誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS)を用いた玄米中カドミウム分析法について妥当性評価を実施した.本法は,玄米を粉砕しマイクロウェーブ分解装置で試料溶液を調製した後,ICP-MSを用いて測定する分析法である.妥当性評価は,成分規格値0.4 ppmとなるようにカドミウムを添加した試料について分析者3名による併行数2で2日間の試験を行った.その結果,「食品中の有害物質等に関する分析法の妥当性確認ガイドライン」の目標値に適合し,分析法の妥当性を確認できた.17道府県産の玄米244検体について実態調査を実施したところ,カドミウムが210検体から検出されたが,成分規格値0.4 ppmを超えるものはなかった. |
| 妥当性評価,カドミウム,玄米,誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS),マイクロウェー ブ |
|
魚肉中の一酸化炭素検査法の改良及び含有量の実態調査 |
|---|
|
魚肉中の一酸化炭素検査法を改良した.厚生労働省から示された通知法における,魚肉の細切方法,均一化方法,魚肉からの抽出工程について検討し,検査の各工程においてばらつきを低減することができた.また,消泡剤として試薬を1-オクタノールからシリコンに変更し,さらに,硫酸の使用量を通知法の半量にできることを確認した.改良した検査法を用いて,一酸化炭素の低減なく試料を保管できる条件の検討を行ったところ,冷凍で7日間は保存可能であることを確認できた.また,まぐろとぶりの一酸化炭素含有量の実態調査を行った.市販のパック入りぶり4検体から使用の判定基準を超える値を検出したが,魚肉から発生するバックグラウンド値と判断した.今後,行政検査の結果を判定する際の一助となるデータが得られた. |
|
一酸化炭素,食品添加物,魚肉,まぐろ,ぶり,含有量の実態調査 |
|
乳等の容器包装におけるヒ素試験法の改良 |
|---|
|
乳等の容器包装におけるヒ素試験の改良法として,硝酸マグネシウム・エタノール溶液存在下で試料分解後,水素化物発生装置付原子吸光分光光度計で測定する方法(以下AAS法とする),及び,マイクロウェーブで試料分解後,ICP-MSで測定する方法(以下ICP-MS法とする)を検討した.AAS法では,チタンや鉄を含有する試料を除き,回収率は80%以上を示した.ICP-MS法では,酸分解液として硝酸・塩酸混液を用いることで,AAS法で適用できる容器包装に加え材質にチタンを含む試料でも回収率は良好であった.AAS法及びICP-MS法は,試験時間が短く,有害ガスを生じない方法であるため,公定法の代替として適用可能であると考えられた. |
|
食品衛生法,ヒ素,原子吸光分光光度法,マイクロウェーブ,ICP-MS,容器包装 |
|
蛍光X線分析装置を用いた玄米中臭素の分析法-試料粒度と加熱乾燥条件の検討- |
|---|
|
蛍光X線分析装置を用いた玄米中の臭素分析法について,最適な前処理条件の検討を行った.本法は,玄米試料を細かく粉砕し,加熱乾燥により試料中の水分を除き,加圧成型機でペレットに成形したものを蛍光X線分析装置にて測定する.今回,前処理操作のうち,玄米試料の粉砕粒度と加熱乾燥の条件について検討した.粉砕粒度条件については,試料表面の粒度の均等性がX線強度に与える影響を検討した.その結果,目開き425 µmのふるいを用いて粒度を均等にした試料はペレットが崩壊しやすく,測定用試料とすることが難しかった.一方で,ふるいを省略した簡易粉砕試料では,十分な強度のペレットを作製することができ,X線強度の感度も良好だった.また,試料中の水分含量がX線強度に影響することから,加熱乾燥条件を検討した.その結果,加熱温度100及び130 °Cは2時間以上,150 °Cは0.5時間以上で十分なX線強度が得られた. |
|
臭素,玄米,蛍光X線分析装置,粒度,ペレット,加熱乾燥 |
|
輸入農産物中の残留農薬実態調査(令和4年度)-野菜類及びその他- |
|---|
|
令和4年4月から令和5年3月までに都内に流通していた輸入農産物のうち,野菜,きのこ類,穀類及び豆類の計43種199作物を対象に残留農薬実態調査を実施した.その結果,22種72作物(検出率36%)から殺虫剤,殺菌剤,除草剤及び共力剤合わせて56種類の農薬を検出した.検査項目農薬の検出濃度は痕跡(0.01 ppm未満)~0.56 ppmであった.検出農薬の内訳は,野菜では17種64作物から殺虫剤24種類,殺菌剤24種類,除草剤2種類が検出された.一方,穀類では3種4作物から殺虫剤5種類,殺菌剤5種類,共力剤1種類が,豆類では2種4作物から殺菌剤2種類が検出された.このうち,3作物から一律基準値又は残留基準値を超過する残留農薬が検出された.野菜では,中国産未成熟えんどう1作物からジニコナゾール0.10 ppm(一律基準値0.01 ppm)及びプロピコナゾール0.18 ppm(残留農薬基準値0.05 ppm)が,タイ産未成熟えんどう1作物からジニコナゾール0.27 ppm(一律基準値0.01 ppm)及びプロピコナゾール0.30 ppm(残留農薬基準値0.05 ppm)が検出された.カナダ産レンズ豆からは,トリフロキシストロビン0.02 ppm(一律基準値0.01 ppm)が検出された.これらはEDI/ADI比から推定し,当該作物の喫食により健康被害が生じる可能性は低いと考えられた. |
|
残留農薬,輸入農産物,殺虫剤,殺菌剤,除草剤,共力剤,残留基準値,一律基準値,推定一日摂取量(EDI),一日摂取許容量(ADI) |
|
輸入農産物中の残留農薬実態調査(令和4年度)-果実類- |
|---|
|
令和4年4月から令和5年3月までに都内に流通していた輸入農産物のうち,果実類の18種131作物を対象に残留農薬実態調査を実施した.その結果,15種71作物(検出率54%)から殺虫剤及び殺菌剤合わせて52種類の農薬を検出した.食品衛生法の残留農薬基準値の対象部位のうち,検査項目農薬の検出濃度は痕跡(0.01 ppm未満)~1.1 ppmであった.検出農薬の内訳は,かんきつ類では4種15作物から殺虫剤12種類,殺菌剤2種類であった.ベリー類では3種13作物から殺虫剤12種類,殺菌剤21種類が,その他の果実では8種43作物から殺虫剤19種類,殺菌剤19種類が検出された.このうち,オーストラリア産ぶどう1作物から殺虫剤ビフェントリンが1.1 ppmと食品衛生法で定める基準値0.7 ppmを超えて検出された.本作物におけるビフェントリンの推定一日摂取量(EDI)と一日摂取許容量(ADI)との比(EDI/ADI比)は6.5%であった. |
| 残留農薬,輸入農産物,果実,殺虫剤,殺菌剤,残留基準値,一律基準値,推定一日摂取量(EDI),一日摂取許容量(ADI) |
|
国内産野菜・果実類中の残留農薬実態調査(令和4年度) |
|---|
|
令和4年4月から令和5年3月までに都内に流通していた国内産農産物のうち,野菜20種64作物,果実類6種12作物について残留農薬実態調査を行った.その結果,20種45作物(検出率59%)から殺虫剤,殺菌剤及び除草剤合わせて50種類の農薬を検出した.このうち,検査項目農薬の濃度は痕跡(0.01 ppm未満)~0.32 ppmであった.検出農薬の内訳は,野菜では15種34作物から殺虫剤22種類,殺菌剤16種類が検出された.一方,果実類では5種11作物から殺虫剤14種類,殺菌剤10種類,除草剤1種類が検出された.検出頻度の高かった農薬はアセタミプリドで,野菜4作物,果実5作物から検出された.なお,食品衛生法の残留基準値または一律基準値(0.01 ppm)を超えて検出された農薬はなかった. |
| 残留農薬,国内産農産物,野菜,果実,殺虫剤,殺菌剤,除草剤,残留基準値,一律基準値 |
|
畜水産物中の残留有機塩素系農薬実態調査(令和4年度) |
|---|
|
有機塩素系農薬による健康危害を未然に防ぐため,東京都内に流通している畜水産物中の残留実態調査を継続的に実施している.令和4年度は,食肉,生乳,鶏卵,魚介類及びその加工品等,畜水産物10種122食品について調査した.その調査結果から,各食品毎に設定された残留基準値を超えていないか,また,既報と比較して残留の変遷について考察した.食肉,鶏卵からは有機塩素系農薬を検出しなかった.一方,生乳7食品,ウナギ3食品の合計10食品(検出率8%)から4種類の有機塩素系農薬(BHC,DDT,ヘプタクロル及びヘキサクロロベンゼン)を0.0001-0.008 ppmの範囲で検出した.これらの農薬はこれまでにも検出例を報告している.有機塩素系農薬の使用が禁止され長期間が経過した現在においても,乳牛やウナギの飼育環境中に低濃度での残留が続いていることから,今後も継続調査が必要である. |
| 残留農薬,畜水産物,有機塩素系農薬,残留基準値 |
|
東京都における食品中残留農薬一日摂取量調査(令和3年度) |
|---|
|
令和3年5月から7月に東京都内で購入した食品(94種類300品目)及び8月に採取した水道水を試料としてマーケットバスケット方式を用いて残留農薬の一日摂取量を調査した.残留農薬は,IV群(油脂類),VI群(果実類),VII群(緑黄色野菜)及びVIII群(その他の野菜・きのこ・海草類)からジノテフラン,ボスカリド及びトルフェンピラド等11農薬が0.001~0.046 ppm検出された.喫食した場合における各農薬の推定一日摂取量(EDI)を算出し,一日摂取許容量(ADI)と比較したところ,EDI/ADI比は0.0021~1.4%であり,ヒトへの健康影響は懸念されるレベルにはないと考えられる. |
| トータルダイエット,残留農薬,一日摂取許容量(ADI) |
論文Ⅳ 生活環境に関する調査研究
|
東京都西部におけるマダニの生息状況実態調査(平成29年度~令和3年度) |
|---|
|
東京都西部にはシカやイノシシなどの野生動物が生息しており,これらの動物に外部寄生するマダニが生活環を維持しうる環境である.東京都内のマダニ生息状況を把握するため,平成29年度から令和3年度まで,東京都西部に定点を設置し,旗ずり法によりマダニの採集調査を実施した.調査の結果,種不明の若虫及び幼虫を除き3属11種5,068匹のマダニが採集された.最も多く採集されたのはヒゲナガチマダニ,次いでオオトゲチマダニであり,幼虫を除き採集されたマダニの87%を占めた.近年,東京都を推定感染地とするマダニ媒介感染症の届出は無いものの,近隣県では発生が見られることから,発生時に備え平常時から都内のマダニの生息状況を把握していく必要がある. |
| マダニ,マダニ相,東京都,衛生動物,季節変動,ヒゲナガチマダニ,オオトゲチマダニ,フタトゲチマダニ |
論文Ⅴ 生体影響に関する調査研究
|
大気汚染物質としての球状高純度酸化鉄粒子の走査型電子顕微鏡観察 |
|---|
|
大気降下物中に含まれる球状の高純度酸化鉄粒子を,走査型電子顕微鏡を用いて観察した.2020年6月から2022年12月までに捕集した大気降下物を観察し,粒径100µm以下の吸引性酸化鉄粒子を3,401個見つけ出した.そのうち,2,217個(約65%)は粒径10µm以下の咽頭通過性酸化鉄粒子で,さらに498個(約15%)は粒径4µm以下の吸入性酸化鉄粒子であった.酸化鉄粒子は形態別に,標準型(N型),6種類の派生型(N2~N7型),回転型(R型)および崩壊型(B型)の9種類に分類された.観察した酸化鉄粒子数には,季節変動性などの経時変化や,粒子形態との有意な関連性は見られなかった.崩壊型には,標準型,各派生型そして回転型に類似する酸化鉄粒子があり,どの形態の粒子であっても同様な生成過程を経ているものと推察された. |
|
大気降下物,大気汚染物質,球状酸化鉄,じん肺,走査型電子顕微鏡 |
論文Ⅵ 精度管理に関する調査研究
|
衛生検査所精度管理調査における生化学検査への試料の配付手段が及ぼす影響 |
|---|
|
東京都は,衛生検査所精度管理調査の一環で,都内の医療機関を介して衛生検査所を対象としたブラインド調査を実施している.令和4年度の調査では,調査試料を医療機関へ配付する方法を一部変更したことから,配付過程における搬送方法の違いが生化学的検査項目の結果に影響を及ぼすかを検討した.また,実際の調査結果を再解析し,搬送方法別に比較を行った.その結果,従来の搬送方法を模した用手搬送と輸送車搬送の間で,測定した13項目はいずれも同等な結果であった.また,令和4年度の東京都衛生検査所精度管理調査において,従来法で試料を配付した10施設及び輸送車法で配付した13施設の結果を比較したところ,平均値に乖離はなかった.しかし,施設間差の減少が,輸送車法を用いた7項目において確認された.今回の検討では,ブラインド調査において,搬送の条件変更が調査に重大な影響を及ぼす可能性は低い一方で,搬送方法を統一化することが,一部の検査項目の施設間誤差を減少させる結果となった.これにより輸送車法による統一的な配付手段の有用性が確認された. |
| 臨床検査,衛生検査所,生化学的検査,ブラインド調査,外部精度管理,検体輸送 |
|
東京都における水道水質検査の外部精度管理調査結果(令和4年度) |
|---|
|
東京都では,「東京都水道水質管理計画」に基づき,東京都健康安全研究センターが中心となり,水道事業者及び厚生労働大臣の登録を受けた水道水質検査機関を対象とした外部精度管理を実施している.本稿においては,令和4年度に実施した「フッ素及びその化合物」(以下,「フッ素」とする)及び「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」(以下,「1,2-ジクロロエチレン」とする)に関する外部精度管理の概要を報告する.フッ素には37機関が参加し,全ての検査機関が評価基準を満たしていた.一方,1,2-ジクロロエチレンには36機関が参加し,このうち1機関が評価基準を満たさなかった.その原因は,分析に使用した機器の不具合によるものであった.また,検査実施状況において,国の標準検査方法に準拠していない検査機関が見られた.これらの検査機関は,検査実施標準作業書を見直すとともに国の標準検査方法を遵守した適正な検査を実施する必要がある. |
| 外部精度管理,水道水,フッ素及びその化合物,シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン,告示法 |